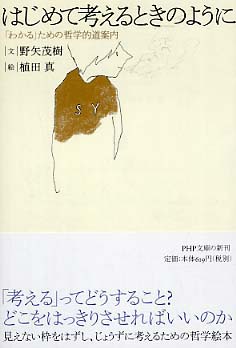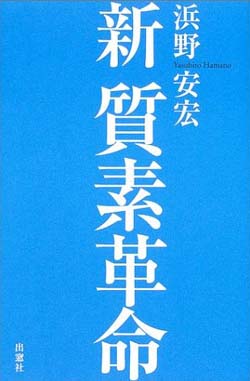MEMBERSHIP | ビジネス / プロダクト
2025.08.18 19:02
フリーランスで活躍するプロダクトデザイナーたちのスキルの根底には、インハウス時代の経験がどのように積み重ねられ、影響を与えているだろうか。それぞれ異なるメーカーに勤務した経験をもつ、柴田文江、鈴木 元、北川大輔の3人が、インハウス時代の仕事や独立の経緯、現在のインハウスデザインとの関わり方について語る。

企業だからできた経験と学び
──新卒でメーカーに就職したときのことを教えてください。
柴田文江 私の学生時代はフリーランスのプロダクトデザイナーが今ほどいなかったので、まずメーカーに入って実践的に勉強したほうがいいと思っていました。いずれフリーになることを念頭におきながら、東京にあって、女性が働きやすいと聞いた東芝を選びました。
鈴木 元 当時、プロダクトデザインって、大学を卒業してすぐに独立する選択肢があまりなかったように思います。僕もメーカーに就職することに迷いはありませんでした。もともと道具類が好きだから家電かな、というくらいで。大学3年生のときにインターンを経てパナソニックに就職しました。
北川大輔 僕は鈴木さんの大学の後輩にあたるのですが、確かに、大手メーカー志向が主流でした。メディアではフリーランスデザイナーの活躍を目にして憧れましたが、大学ではモビリティか家電か、大きくふたつに分かれるところで家電を選び、NECデザイン(現NEC)に就職しました。
──インハウスデザイナー時代にはどのようなデザインを担当していましたか?
柴田 家電小物チームに配属されて、例えばカールドライヤーの新しいアタッチメントを考えたり、それのモデルチェンジも担当したり。短期間で何十個もの商品をつくることができたんですよね。ゼロから企画し発売するまでを何度も経験できたのは、ありがたかったです。
鈴木 僕が就職した頃は、いわゆるガラケーが誕生して、出せば売れるほど業界が盛り上がった一瞬の華やかな時代で(笑)、まさにその携帯電話を担当していました。半年に1回のペースでモデルチェンジするような、ちょっと異常な市場の熱狂がありましたね。だから、朝から終電までずっと働いているような毎日。でも、数十万、数百万個単位で売れるような商品だったので街で見かけると嬉しいし、刺激的ではありました。
北川 僕は最初はパソコンチームでラップトップや液晶一体型のデザインを担当して、入社4年目からは、携帯電話のチームに配属されました。アンドロイドが登場した前後のちょうど過渡期で、スマートフォンも多く担当しました。ほかにもスーパーコンピュータ、空港の発券機や管制室用の機器類のようなBtoB分野にも関わっていました。