
『x‐DESIGN―未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾出版会)の著者による連載第4弾の今回は、加藤文俊教授と藤田修平准教授による対談。どちらにも共通しているのは、人に会い、コミュニケーションをとり、作品をつくるという実生活に溢れている行動。フィールドワークの加藤文俊とドキュメンタリーの藤田修平が語る「デザイン」への思いとは。
「観察」を習慣に
藤田修平(以下、藤田)
原稿、大変興味深く読ませていただきました。そこで伺いたいのですが、加藤先生のフィールドワークにおいて、外から見る「観察」と中に入って行く「参与」の2つの方法をどう使い分けられているのですか。
加藤文俊(以下、加藤)
僕の場合は、「観察」と「参与」の2つに分けるのではなく、ステップだと考えています。第一段階はどんなに些細なことでもいいから、じろじろじっくり見るということを日常的なふるまいにしておくんです。そうやってとにかく周囲を気にしながら暮らしていると、人に対する関心とか、暮らしに対する興味って、自分の中で浮かんでは消える、消えては浮かぶ、という感覚に変わる。
最近、企業の商品開発やサービスをデザインしている方からフィールドワークのやり方を聞かれることがあるのですが、そのときにまず言うのは、1回や2回街に出てみたからといって、アイデアは出てこないし、新しい商品がすぐさま生まれることはないということなんです。観察することを習慣化・日常化することが大切だ、というのが僕の持論です。
気づくことから生まれる人への関心、暮らしに対する興味という、ある種の「おせっかい」のような想いがデザインという行為への衝動なのだと思っています。

藤田
また、興味を持ったのが「キャンプ」です。「キャンパス」とは語源が同じなのですね。ただ、キャンパスと対比されていて、ある場所に人が集まって、新しい出会いとかその場所の特徴に刺激を受けることで、創造性を求める方法とされていました。その例として、この本では、田辺市で行ったフィールドワークとポスター制作が書かれています。前もって下調べや綿密な計画を立てるのではなく、街を歩いてみて、気づいたことを絵メディアに落とし込む試みはすごく面白いですよね。この過程はドキュメンタリーと似たところがあると感じました。

加藤
僕たちの活動の特質は、「キャンプ」という言葉に集約されていると思っているのですが、これは、じつは友人と話していて「それキャンプですね」って言われたのをきっかけに使い始めました。もう一方で、まだ十分に語りきれてないのが「キャンプ場」みたいな話なんですよね。ドキュメンタリーで言うキャンプ場は、ロケ地だと思うんです。だから、いくらキャンプの道具立てを考えたり、実践の方法を工夫したりしても、結果的に良いキャンプ場にめぐりあわないとうまくいかないことがある。ドキュメンタリーにしても、ある程度ストーリーラインが見えつつ撮影をしていくと思うのですが、多分、途中で方向性が変わることもあるはずです。
フィールドワークも予定調和的に、準備どおり画を撮って組み合わせるというよりは、語っている中から実は新しい問題点とか新しく撮りたくなる画が出てくることがある。
だから、現場に行ってから、手持ちの道具と与えられた環境と、巡り会った人たちをまず理解して、そこでいちばん楽しいのは何かということに向けて、最大限努力する。出かけた先での出会いによって、調査や取材が予期せぬ方向に動いていくというリアリティは、フィールドワークの教科書には書いていない、別の世界があるように思います。
藤田
ドキュメンタリーの場合、「日記映画」と呼ばれるような、個人的な体験をその場その場で撮影していって、1つの作品にするといった実験的な映画もありますが、あらかじめ作品の枠組みを想定しておくほうが多いです。そして、現場で修正していくと。その意味ではフィールドワークのほうが自由なのかもしれません。ドキュメンタリーとの共通性で言えば、出会った人に取材をして、ポスターにした後、その人をポスター展に招待しています。それはドキュメンタリーの上映会で出演者とか、関係者を招待するのと似ていると思いました。
たった1度きりの「場」
加藤
その話、僕も藤田さんに聞きたいなと思っていました。僕が藤田さんの研究会の作品で印象的だったのは、『還暦野球』なんです。取材している間に、出演者の方が亡くなってしまった。そういうドラマやハプニングに立ち会いながらも、作品を完成させるわけじゃないですか。映画作品が評価されて賞をもらう、もらわないという話とは別に、その人の生きている姿を藤田さんは映像に収めてしまった。僕たちのやっている「キャンプ」は1泊2日のポスターづくりだけれど、映像というかたちである意味もっと深く関わることで、そこに映る人の人生のドラマに付き合いながら活動しているわけですよね。 楽しさもあるんでしょうけど、重さもある。そのあたりは、どう感じていますか?

▲『還暦野球』(監督:金森誠、制作:山本大輔、2005年)
藤田
『還暦野球』(監督:金森誠、制作:山本大輔、2005年)では出演者の方が亡くなって、ORFでの最初の上映会にその奥さんを招待したのですが、映画を見ながら泣かれているのです。やはり関係者の方々と一緒に観るとき、映画から受ける印象が異なりますね。また、こうしたとき、上映後に監督が観客に映画の登場人物を紹介するのですが、上映会が1つの「場」になります。インタビューの撮影でも、ライトをセットして、マイクをつけてもらって、みんな静かにして、録音のボタンを押して、「では、お伺いします」と語りかけるとき、そこが日常と離れた世界になって、インタビューを受ける方の感情が高まることがよくあります。これもそうした「場」と言えるのでしょうね。
加藤
そうですよね。
藤田
そういう意味では、映画はメディアとしては残るけれど、上映もポスターの展示も1回限りなのですね。
加藤
映像作品は繰り返し再生できる。ポスターも紙媒体なので持ち運びができるのですが、その「場」ができるのは1回きりなんですよね。 いま藤田さんが言われたドキュメンタリー上映の「特別な場所」みたいな感覚と多分似たようなことを僕も経験しています。ポスターをつくった翌日に、そのモデルになった本人が来て、初めてそれを観てもらって、それを観ながら語るという「場」は、ほんのわずかな瞬間。


▲田辺市立旧図書館で開かれた「田辺の人びとのポスター展」(2012)
「田辺キャンプ 場のチカラプロジェクト」
藤田
ところで、取材のとき、こちらが撮りたいなと思ったものと相手の方の振る舞いがずれることがあります。例えば、農家の方の場合だと、撮影と聞いて正装されたり。でも欲しいのは普段のままの農作業の姿だったりします。
加藤
1つ面白かったのは、つくり酒屋の若社長に学生がインタビューに行ったときに、いま藤田さんが言ったみたいに、取材に合わせてきちっとネクタイをして、若社長の格好をしていたんですよ。でき上がったスーツ姿のポスターを観に来た人たちは「なんでお前はネクタイなんかしているんだ」って笑ってました。これはとてもチャーミングな話で、学生が来て取材してポスターをつくるということが、彼の洋服を変えさせたんです。
藤田
彼を知っている人がポスターを見て、普段の姿との差を面白がるのですね。
加藤
そうそう。これって、藤田さんが先ほど述べていた、被写体になっている人たちと一緒に撮った映画を観る「場」と似たような意味合いがあるんだと思います。結局、ポスターをつくる人とか映像を撮る人っていうのはいるけど、当然その人たちだけでは完成しえない。映される人とか撮られる人という関係性があって、ともに完成形があるんですよね。僕はそこに居合わせて、「特別な場所」にいられたということだけで報われて、すがすがしい気持ちになるところがありますね。
*さらに詳しい内容については、x-DESIGNのこれまでの研究活動と所属する10名の教員それぞれの思想的背景をまとめた書籍『x‐DESIGN―未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾出版会)をご覧ください。
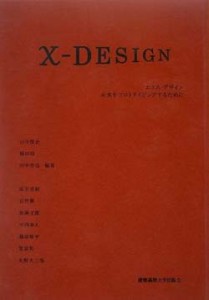
*第5回(最終回)に続きます。












