
『x‐DESIGN―未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾出版会)の著者による連載最終回は、坂井直樹教授と田中浩也准教授による対談。日本だけでなく、世界に衝撃を与えるものづくりをしてきた坂井直樹と、そもそもものづくり自体に革命を引き起こそうとする田中浩也。ものづくりに深く携わっているふたりにとって、デザインはどんな意味を持つのか。
グッドデザインとバッドデザイン
田中浩也(以下、田中)
私は、FabLabやパーソナルファブリケーションと呼ばれる「ものづくりを人々の手に取り戻そう」という活動をしていますが、パーソナルファブリケーションの思想的な源流の1つは、スチュアート・ブランドの制作した『ホールアースカタログ』にあると言われています。『ホールアースカタログ』はヒッピー向けの雑誌でしたが、坂井さんはちょうどそれがアメリカで発行された頃に、実際に現地にいらっしゃったかと思います。当時はどんな状況だったのでしょうか。
坂井直樹(以下、坂井)
僕がアメリカに行ったのは60年代のことでしたが、当時はウーマンズ・レボリューションや「ブラックパワーといったマイノリティを解放しよう」「僕たちが社会を変えるんだ」みたいな若者たちによる活動が盛んで、世の中が本当に変わるんだと思っていましたね。
当時、僕は京都で出会ったヒッピーの知り合いを訪ねてヒッピーたちが集まっていたサンフランシスコに行ったんです。もともと僕は日本では京都藝大に通っていたんだけれど、当時の京都は今とは全然雰囲気が違って、いわゆる反体制の外国人がたくさんいたんですよ。その中にはヒッピーたちもいて、彼らと交流しているうちに、彼らの「バッドデザイン」にすっかりはまってしまったんです。おかげで、大学で教えられているような「グッドデザイン」やメインストリームのバウハウス・デザインにはまったく馴染めずに、1年半で大学を辞めてしまった。
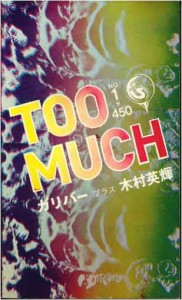
▲60年代後半のサンフランシスコのストリートを撮影した書籍『TOOMUCH』を出版。
田中
ところが帰国されてからは一転、デザインカンパニーを立ち上げられたんですよね。

▲ファッションデザイナー時代の貴重な写真、anan創刊号の多くのページを飾った。
坂井
そうですね。1970年はアパレル元年と呼ばれているけれど、当時はひじょうに少ない資本でアパレルビジネスを始められたんです。生地は手形で買えて、縫製工賃さえ払えばよかった。田中さんにとってのインターネット革命に似ているかもしれません。僕が帰国したときは「コムデギャルソン」を立ち上げた川久保玲さんや、4℃がデビューしたばかりで、僕も彼らと店舗スペースをシェアしてアパレルビジネスを始めました。

▲帰国後初めて持った服づくり工房WATER、自分たちでつくり、自分たちが持っていた原宿のブティックHELPで販売した。
この頃から、僕は三菱レイヨンとか東レみたいな大企業にも出入りし始めました。大学を卒業すると普通の人はそのまま大企業に就職すると思うんだけど、僕はそもそも大学を途中で辞めちゃって、そういった仕事にまともに関わる機会がなかったから、逆に興味があったんですね。日産と付き合い始めたのはその後です。
田中
山中俊治さんとお会いしたのは日産で仕事をし始めてからですか?
坂井
そうですね。ただし、日産では山中さんとは何も一緒にやっていません。仕事をしたのは山中さんが日産を退職してからで、O-productが初めて。O-productが世に出た少し後にバブルがはじけるんですよね。あれは想定外だった。

ただ、同時にこの頃には海外のメディアの取材がすごくたくさんきていました。バブルのときには日本が世界でいちばんの金持ちになるぞ、と言われていたから、海外のメディアは日本にすごく注目していたんですね。金持ちになったいちばんの要因は、高度成長期を支えた工業だったわけですが、この時代はまだ日産の「中村史郎」みたいに個人名を出せず、トヨタや日産がデザインしているという言い方だった。だから、みんな企業に所属しないフリーの僕の名前しか知らなかったんですね。その結果、僕がものすごく海外メディアに出ることになった。

▲掲載された海外メディア
SFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)で働くことになったのはその後ですね。それまでいろんなところで講師はしたことがあったけど、レギュラーで大学の教員になるなんてまったく予想してなかった。ただ、そういう人生もいいかと受け入れられた5年間でしたね(笑)。
ミシンと3Dプリンタ
田中
今回本の中でも書いたんですが、僕はSFCに来てから、物質的なものに多く取り組むようになったんです。それ以前は主にソフトウェアでした。ただ、SFCに来てみるとそうした授業は既にたくさんあったし、ITのカルチャーもあった。そこで電子工作などを自分で勉強しながら授業でも教えることにして、ソフトウェアをネットワークやサービスと絡めた物理的な「もの」をつくり始めました。ただ「プロダクト」というよりは、どちらかといえば「デバイス」的なものでした。それもひじょうに個人的な関心から発想したものです。

▲筧 康明准教授と久下 玄と一緒に開発した路面の色を読み取りサーバーに送れる杖。
坂井
昔は植物と会話するデバイスとかつくっていたそうですね(笑)。
田中
そうなんですよ。アマチュアが電子工作を学ぶと、いろいろな「もの」にコンピュータを埋め込み始めます。そうすると、既存のカテゴリーに収まらない、ひじょうにユニークなものが生み出され始める。それはどうも、いわゆるプロダクトデザインともコンピューター・ヒューマン・インターフェイス(CHI)とも違う。そういった作品からは、むしろ自分の好きな「もの」ともっとインタラクションをしたくて、コンピューターを手段として使っているように思えたんです。それが何なのだろうともがいていたら「パーソナルファブリケーション」という言葉を知った。それで世界が開けたのです。3Dプリンタやレーザーカッターがすごい!といった技術への好奇心よりも、そういった、自分のつくっているものは何なんだろう、と模索していたら、パーソナルファブリケーションと出会った形です。
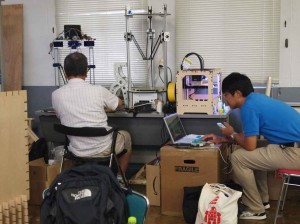
▲今話題の3DプリンタはFabLabではつくるための道具であるだけではなく、つくる対象でもあります。
坂井
田中さんがいま広めている、3Dプリンタで世界が変わるっていう話は、僕の世代はミシンで同じことを考えたんですよ。みんなミシンがあって、みんな服がつくれる。これはすごいことだ!と僕らは思っていたけれど、いまの世の中を見てみると、ほとんどの人はミシンを持っていないし、たとえ持っていても服なんてつくらない。
田中
「もの」をつくる動機や必然性が必要ですよね。理由よりも欲望に近いかもしれませんけど。そういう意味では、僕のような何かつくりたいものがある人間にとってはすごくいい環境になりました。「つくる」ことの意義を深く考えるための「メディア」として、3Dプリンタには一定の価値があると思います。「ワープロ」のようなものです。それを目の前にして初めて、一体自分は何を書きたいのかを考え始める。それを通じて、社会で何をしようとするかが大事ですよね。

坂井
逆に、そういう意味で本当に何かをつくりたいって思っている人にとっていまの時代は最高だよね。パッケージ、電子工作、プログラミングが全部自分たちでできるようになった。ベンチャー企業にとってはすごくいい環境なんじゃないかな。

▲FAB9で行われた、「巻き寿司」をつくるワークショップ
田中
ただ、いまの若い子たちにそういったチャレンジ精神を教えるのって難しくて……。もちろん、一人ひとりの性格とか質も関わってくるとは思うんですが、社会状況の影響がいちばん大きい気がしますね。
坂井
社会的に戦うべき相手がいないというのは大きい気がするね。ただ、コンサバティブな若者たちを見ているといらだつよね(笑)。
田中
だからこそ、僕はFabLabを国際的な競争が体験できる場にしていきたいと思っています。国境を越えて、リミックスしたり、自分の中のレパートリーを増やしたりして、それらを組み合わせて新しいものをつくる。
そういった意味ではエクス・デザインも、学生だけではなく、教員同士も常に多様な価値観をぶつけ合い、それぞれが本気で未来をつくっているような場にしていきたいですね。

▲今年の8月には世界中のFabLab代表者が集まる、第九回世界FabLab会議(FAB9)が横浜で行われた。
坂井
僕も5年間でしたが、エクス・デザインの他の先生、学生からはすごい刺激を受けました。やっぱり、ここに来たことでアップデートできた感じはありますね。もしここを通過してなかったらただの年取った、元クリエーターになっていたような気がします。
*さらに詳しい内容については、x-DESIGNのこれまでの研究活動と所属する10名の教員それぞれの思想的背景をまとめた書籍『x‐DESIGN―未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾出版会)をご覧ください。












