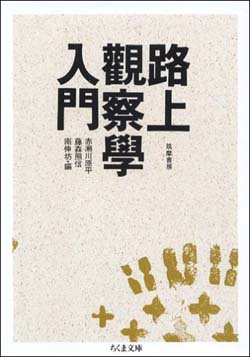『生きられた家 経験と象徴』(岩波現代文庫 1,000円)
評者 みかんぐみ・竹内昌義(建築家)
「なんでだろう? できが良くても、居心地が悪い建築」
通常、建築の本はそれぞれの専門に即して書かれているので、その立場を了解しなければならない。日本古来の民家なら民家のこと、現代的なデザインならそういったものを扱う人が、それぞれの立場から文章を書く。それは建築というものが、すでにいくつもの分野に細分化されたことを意味している。
しかし、この本で扱われている建築、空間の概念は広い。建築家のつくった空間から民家の空間まで、広く人間と空間の関わりである。それは例えば、引っ越した先の空間が、だんだんと住み手に馴染んでいくような関わりだ。この本は建築家の身勝手な方法論ではない。むしろ、もっと普通に起こり得ること、住宅というよりも「家」という概念が持つ、ある親密な雰囲気とは何かといったこと、あるいは身体的な認識論である。
「生きられた家」とは、人が経験することによって家(空間)の質が確実に変化する、その変化を捉えた言葉である。また、「空間が生きられる」とは、そこでの住まい手が空間へ関わることによって引き起こされる、空間の変化のことである。
私がこの本を最初に読んだのは、大学の研究室に入ったばかりで、建築をつくることへの興味だけが強く、「生きられた空間」とつくるべき空間との距離がなかなかうまくとれなかったときだ。認識論は認識論、つくることとは別物だと考えたかった。その一方で、そういう単純化した二分法に、なんとも言えない心地悪さを感じていた。その頃にどんな家に住みたいか、ということが話題になったことがある。当時の私は「建築家の家ではなく、古い日本家屋がいいと思う」とすぐさまに答えた。私としては建築家の恣意性が、生活に入り込んでくるのを排除したかったのだ。
建築家がつくった空間は、時としてひじょうに居心地が悪いものだ。建築としてはとても良い空間ということが頭では理解できても、窮屈なのである。ひとことで言うと、なんとも“フィットしすぎている”のである。ぴたっとしていて、遊びがない。融通が利かなそうだ。言説に忠実なのだと言われればそれまでだが、与件の変更や突然の出来事で前提が崩れてしまいそうな危うさがある。
建築に直接関わるようになった今も、建築に対して漠然と感じていたことは、ほとんど変わってはいない。むしろ、もっと強くなった。コントロールが利きすぎ、それ自身が饒舌な空間にはほとんど魅力を感じない。空間は、もっと生活に対する“バックグラウンド”でいいのではないかと思っている。言葉では難しいが「ちょうど良さ」が大事だという気がする。生きられる余地を残すために、ルーズな部分が必要だ。
だからと言って、伝統的な家屋や民家に戻るほど、ノスタルジックな感覚にもなれない。現代の建築では対応すべきことも格段に増えているし、未来も見えにくい。だから結果をオープンエンドにしておき、住まい手が自ら手を加えることができるようにしたいと思う。程度の差こそあれ、そうすることが「ジャストな建築」を考えるより、建築をはるかに自由にしてくれるだろう。たいていの建築家は、建築家であることによって大きな足枷をはめていることを自覚していない。建築家は、自らだけで建築を生かせる訳ではないということに気がつくべきだ。
建築や環境デザインに関わるなかで、何をどう取り扱ったらよいかに迷ったとき、自分がどこにいるか、それを判断する一助となる1冊である。さまざまな挿話のバリエーションも面白い。また、文庫版なので手軽である。ポケットに入る「空間への1つの概観」として読んでいただければと思う。(AXIS 103号 2003年5・6月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。