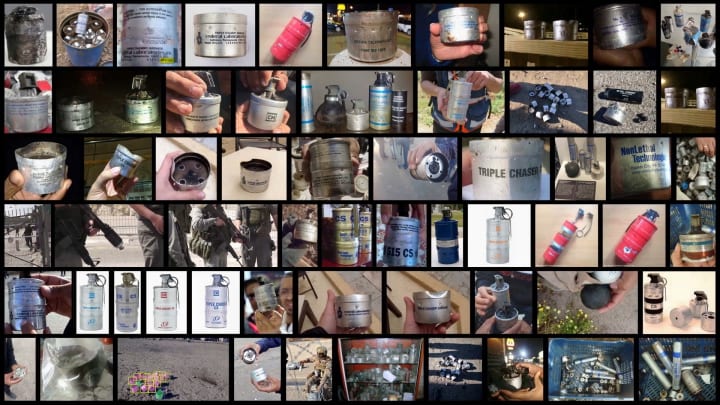REPORT | アート / サイエンス / テクノロジー / 展覧会
2021.12.16 13:55
毎年フランスで開催されるデジタルアートの祭典「ビエンナーレ・ネモ(Biennale Némo)」。今年10月から2022年1月初旬まで続くこのフェスティバルでは、パリを中心とするイル・ド・フランス地方の各地でイベントやカンファレンス、パフォーマンスなどが開かれる。ここでは、アート、サイエンス、テクノロジーの交差点で活躍するアーティストが一堂に会したメインの展覧会「Beyond the Real」を紹介したい。

▲Guillaume Marmin《Passengers》(2020) Photo by Quentin Chevrier
「Beyond the Real」の副題は「デジタルアート、サイエンス、テクノロジーで見えないものを明らかにする」。30組以上のアーティストが集結し、見えないものや言葉にできないもの、知覚できないものにアクセスし、新たな方法で世界を捉えようとする視点を提示した。

▲Stenza《The Nemesis Machine》(2015 – 2021) Photo by Quentin Chevrier

▲NEMO EXPO VERNISSAGE Photo by Quentin Chevrier
痕跡が宿す生命性
ニューヨークを拠点とするメディア・AIアーティストYuguang Zhangの作品《(Non-)Human》(2021)は、生命や人間の起源に関する物理学や宇宙論から生まれた、人間とモノのあいだを探るインスタレーションだ。
人工知能や機械学習が、人間以外の知能の可能性を示したことによって、私たち人間とモノの境界線はますます曖昧になっている。人間とそれらを区別するのに意識あるいは心の有無が挙げられるが、いかにして脳に意識や心が宿るかは、現代科学においても解明されていない謎だ。テクノロジーと人間の共存という観点からは、自然と文化、生命と非生命といった二元論を超えて、人間をその他多くの物質のひとつとみなす脱人間主義的な視点の重要性が問われている。

▲Yuguang Zhang《(Non-)Human》(2021) Photo by Saki Hibino
《(Non-)Human》の展示空間で再現されているのは寝室だ。ベッドには、つい先ほどまで誰かが寝ていたであろう痕跡が残っている。実は、この痕跡をつくり出しているのはAI。しばらくベッドを見つめていると、時間の経過に伴って、少しずつベッドシーツが動いていく。この動きは、実際にこのベッドで寝ていた人の睡眠データ、骨格や関節の動きを学習したAIによって生み出されている。
▲(Non-)Human – Moving Bedsheet from YG Zhang on Vimeo
シーツに残った痕跡は人間そのものではないが、人間の存在を感じさせる抽象的で身体的な表現と言える。アニミズムのように、すべての実体に宿る神や精霊のメタファーをも感じさせる本作は、テクノロジーを架け橋に人間とモノの境界を超えた、二元論的なカテゴリーや対立構造ではない曖昧な関係性を詩的に描いている。
人工のサイが問う遺伝子技術のパラドックス
脱人間中心的な視点へのシフトは、気候変動の問題でも求められている。人間が支配的アクターとして、地球環境を破壊してきたその裏で、多くの種が絶滅に追い込まれた。例えば、2018年3月19日、最後のオスのキタシロサイ「スーダン」が死亡し、同亜種は絶滅したというニュースが報じられた。かつて東・中央アフリカ諸国の草原やサバンナの森林地帯を闊歩していたこのサイは、20世紀に入り、環境破壊による生息地の減少や、人の生命力を高める効能があるとされる角の密猟者によって殺され、個体数が激減し、絶滅への道を辿った。
絶滅への嘆きを希望に変えるべく、科学者たちはバイオテクノロジーを駆使し、スーダンのDNAを用いた実験的な脱絶滅プロジェクトに取り組んだ。

▲Alexandra Daisy Ginsberg《The Substitute》(2019) ©️Alexandra Daisy Ginsberg
こうした事実に着想を得たのだろうか、ロンドンを拠点とするデザイナー/アーティストのアレクサンドラ・デイジー・ギンズバーグの映像インスタレーション《The Substitute》(2019)では、新しい生命体を生み出すことに執着しながら、既存の生命体を軽視する人間のパラドックスを問いかける。ギンズバーグは、人工知能で生成されたデータを用いてオスのキタシロサイを「生き返らせた」のだ。
天井から床までを覆ったスクリーンには、バーチャルな世界を歩き回る等身大のサイの姿が映し出される。この人工サイは、哺乳類の特殊な脳細胞であるグリッドセル(空間を移動するための細胞)を持たない状態から始まる。サイは、バーチャルな空間を動き回るうちにグリッドセルの表現を発達させ、それに合わせて知能を高めていく。
▲The Substitute, 2019 – Installation view from Alexandra Daisy Ginsberg on Vimeo
環境に慣れ、知性を獲得するにつれ、サイの姿や音はピクセル化されたデータから高解像度になり、本物のような生き生きとした姿へと変化する。映像と同期した別モニターでは、グリッドセルが発達していく様子も表示される。かつて地球上に生きていたサイは、自然の環境から切り離され、サイバー空間の中で息を吹き返す。その瞳は鑑賞者を見つめ返し、一定の成長過程を超えたとき、その存在が消える。私たちは、このサイが、自然の文脈を離れて生命を得た、完全な人工物であることを思い知らされると同時に、生命に対する人間の矛盾する行いを自問させられるのだ。
30人の私が物語る曖昧な自己
DNAに絡む問題は、加速する監視社会における、イメージ認識とその操作にも疑問を投げかける。アメリカのアーティストであり、バイオハッカーでもあるヘザー・デューイ・ハグボルグによる作品《Probably Chelsea》(2009-2021)では、ゲノム情報からヒトの顔を特定する技術を用い、アイデンティティという時代遅れの概念に反論する。
天井から吊り下げられた無数の顔。これは、DNA分析と顔認識システムを組み合わせてアルゴリズムで生成された、アメリカで有名なウィキリークス内部告発者であるチェルシー・マニングの30種類のポートレートコレクションだ。

▲Heather Dewey-Hagborg《Probably Chelsea》(2009-2021) Photo by Saki Hibino
マニングはトランスジェンダーの陸軍兵士で、獄中で男性から女性へ移行するためのホルモン治療を受けていた。政府からの要請により彼女の写真は世間に出回っていなかったが、ハグボルグはマニングから送られてきたDNAデータを解析し、性別、肌の色、目の色、身長、骨格といった得られた複数の結果から30通りの彼女のポートレートを作成した。
▲Probably Chelsea from Heather Dewey-Hagborg on Vimeo
遺伝子データのリンクにより、私たちが誰であり何であるかといった膨大な量の情報を明らかにすることは可能だが、データはさまざまな解釈も可能だ。データがステレオタイプなバイアスのなかで読み取られ、犯罪捜査や法医学などに用いられることも問題視されている。同時に、DNAを、性別や人種といった私たちの自己を定義するアイデンティティの「コード」として解釈することの限界も明らかにしている。この30人のチェルシー・マニングは、それぞれがマニングであり、マニングではないとも言える。自己の定義の曖昧さと社会や他者に定義される自己の矛盾が浮かび上がる作品だ。
フォレンジック・アーキテクチャーが暴く爆発事故
2018年にアート界で権威のあるターナー賞にノミネートされて以来、さまざまな方面から注目を浴びるリサーチ集団フォレンジック・アーキテクチャー。ビエンナーレ・ネモも、彼らをフィーチャーした展示室を設け、その関心の高さをうかがわせた。ロンドンを拠点とする彼らは、建築家、アーティスト、映像作家、ジャーナリスト、ソフトウエアエンジニア、科学者、弁護士らで構成されている。人権団体、国際検察官、環境保護グループ、報道機関から依頼を受け、デジタルモデリングと建築分析、3Dアニメーション、データ解析などを駆使し、政治的なパワーによって意図的に抹消・歪曲される政治闘争や武力紛争といった国際犯罪などを調査し、国際紛争や人権侵害に関連する法廷で証拠資料を提出する。

▲Forensic Architecture《The Beirut Port Explosion》(2020) ©Forensic Architecture, 2021
展示では、2020年8月4日、ベイルートで6,500人以上の負傷者、200人以上の死者、30万人以上の家屋が被害を受けた大爆発の真相に迫った《The Beirut Port Explosion》(2020)、2011年に起こったロンドン北部トッテナムでの、警察による黒人男性(マーク・ダガン)射殺事件を検証した《The Killing of Mark Daggan》(2020)をはじめ、4作品が展示される。

▲Forensic Architecture《The Killing of Mark Daggan》(2020) ©Forensic Architecture, 2021
国家や政府の嘘を突き詰める強力なツールとして、科学技術とアートを駆使し、私たちの社会を変えるために真実を究明する彼らの作品は、社会問題や政治問題などこの世界で真実とされているもの、見過ごされているものに疑問を投げかける。
その他にも、環境エンジニアのテガ・ブレイン、クリティカルエンジニア/アクティビストJulian Oliver、ソフト・ハードウェアデザイナー/ハッカーBengt Sjölénによるスーパーコンピュータ《Asunder》など、環境危機に対する解決策とデータ社会が抱える問題が交差するアイロニカルなインスタレーションもおすすめしたい。作品の詳細については、2020年に取材したベルリンでのメディアアートの祭典トランスメディアーレの記事を参照してほしい。

▲Tega Brain, Julian Oliver, and Bengt Sjölén 《Asunder》(2019) Photo by Luca Girardini
個人的に「Beyond the Real」はやや安易なコンテクストやキュレーションの斬新さに欠ける側面があることは否めなかった。似たようなテーマを掲げる展覧会が多いなかで、先見性や挑戦的なアプローチをより見てみたいという期待もある。
同時に、世界や社会が抱える問題そのものがますます堆積し、変化が求められている。問題の背後に複雑に絡み合う見えないものや言葉にできないもの、知覚できないものにアクセスすることで浮き彫りとなる、歪んだ社会構造や概念を捉えるという意味で、上記のような作品を体験することは良い機会だろう。今、私たちが対峙している問題だらけの現実を超えていくために、求められている視点やアクションを考えるきっかけとして、アーティストが提示するさまざまな問いに触れてみて欲しい。![]()

▲Emmanuel Van der Auwera 《VideoSculpture XX (World’s 6th Sense) 》(2019) Photo by Quentin Chevrier

▲NEMO EXPO VERNISSAGE Photo by Quentin Chevrier