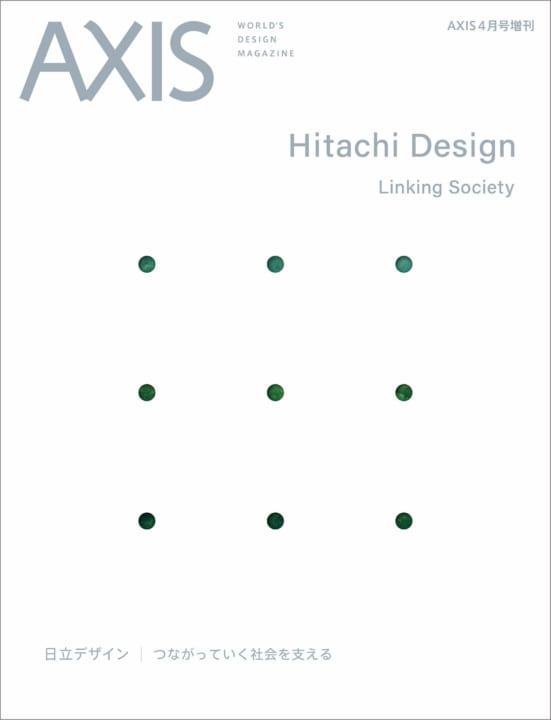PROMOTION | ビジネス / プロダクト
2025.07.01 10:00
RDからプロダクトデザインまで幅広く事業を展開するデザインファーム「フォルム」。ユニバーサルデザインに着目し社会を見据えてきた代表取締役・松本 有氏に話を聞いた。
インタビュー・文/岸上雅由子


2008年リリースの「POP Containers」は、スクエア形状の乾燥食品用保存容器。蓋の中央にある丸いボタンを押すと、ワンタッチでロックが解除される。ボタン部分はそのまま持ち手としても使用可。蓋をする際も、同様の手順で簡単に扱える手軽さ、ユニバーサルなデザインが認められ、国内外のさまざまな賞を受賞。蓋の部分がステンレス製のモデルも含め、OXOのベストセラー製品となっている。
Photos by Michinori Aoki
松本には、大きく人生の進路を変えることになった2冊の本があるという。1冊は高校3年生の時に出会ったイタリアの著名なカロッツェリア「ピニンファリーナ」に関するものだった。「もともとダ・ヴィンチ的なクリエイションに漠然と憧れを持っていたんです」。科学に関心が深く、一方で手を動かすモノづくりにも興味があった松本。クルマの造形的な美もさることながら、あらゆる科学的知識を網羅する設計に一気に魅了され、当初志望を考えていた医学部への進学をやめ、東北工業大学工学部の意匠科に籍を置く。
2年後。今度は公共交通に関する書籍を手にし、再び心を動かされる。「たまたま課題研究のために日本の人口推移について調べていたことから、将来的な人口減少は都市の構造や交通形態に大きな変化をもたらすに違いないと危機感を抱きました」。
松本の視野は、目標としていたクルマのデザインから日用品も含め広範囲な公共のためのモノづくりへと拡大。北欧をはじめ海外事情も調査することで、福祉の充実や高齢者への配慮というデザインの持つもうひとつの役割に気づかされた。「若気の至りで、人口ピラミッド図を片手に県庁や当時の国鉄(日本国有鉄道)にまで足を運び、将来の課題について訴えました。一笑に付されるばかりでしたが、『デザインとは未来を考えることではないですか』と生意気に反論して(笑)。でもその経験から、70年代のはじめ、当時はまだ誰も意識していなかったユニバーサルデザインへの意識が自分のなかにしっかりと根付いたような気がしています」。
大学卒業後、玩具開発メーカーを経て独立。1984年にフォルムを立ち上げた。ベビーカーから多種多様なキッチンツールまで数々のプロダクトを手がけ多くのデザイン賞を手にしていた松本のもとに、2008年、アメリカのキッチン用品メーカーOXO(オクソー)から一通のメールが届く。乾燥食品用の保存容器を開発したいという依頼だった。「重視したのは『誰でも簡単に扱える』というユニバーサルデザインの視点と、収納せずに室内に飾っても絵になるような『魅(見)せる』というアプローチでした」。
製品開発は順調に進むかに思われたが、市場に関する議論のなかで、OXOの社長が「日本向け」という言葉を発した際、状況は一転。松本はすかさず異議を唱えた。別メーカーで携わった保存容器開発の経験から、日本市場向けのモジュールではグローバル展開において制約がかかることを理解していたからだ。「OXOはピーラーで有名になったメーカーです。ピーラーはどんなに素晴らしくても一家庭に1個か2個。でも、保存容器は違います。『全世界に通用する商品を目指しましょう』。最後はそう社長を説き伏せた。クライアントよりも、私のほうが野心家だったんだと思います(笑)」。
握力の弱い子どもや高齢者も意識し、ボタンを押すだけのワンタッチ操作で蓋の開閉を可能にした「POP Containers」は結果的に、08年ドイツの「ユニバーサル・デザイン・アワード」をはじめ「レッドドット・デザイン賞」など、国内外のさまざまな賞を受賞。改良を重ね、世界的ベストセラー商品となっている。
松本は現在、大学で教鞭をとるかたわら、設計スキルのみならず、収入面から経営センス、科学的素養、さらには知的財産権に至るまでデザイナーが身につけるべき全方位的な知識についてその重要性を説いているという。
「デザイナーの社会に対する影響力は計り知れない。デザイナー自身があらゆる意味で豊かでなければ、誰もが豊かさを享受できる社会に変えていくことはできません」。松本にとって、デザインとは単なる造形行為ではない。コーポレートヴィジョンに掲げているように、企業の「想いをカタチにする」ことで社会に貢献していこうとする理念なのだ。

松本 有/1952年生まれ。東北工業大学工学部工業意匠科にてデザインを学ぶ。84年にフォルムデザイン有限会社を設立。2003年株式会社フォルムに社名を変更。公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)理事を務める。