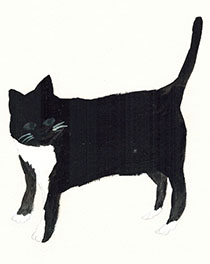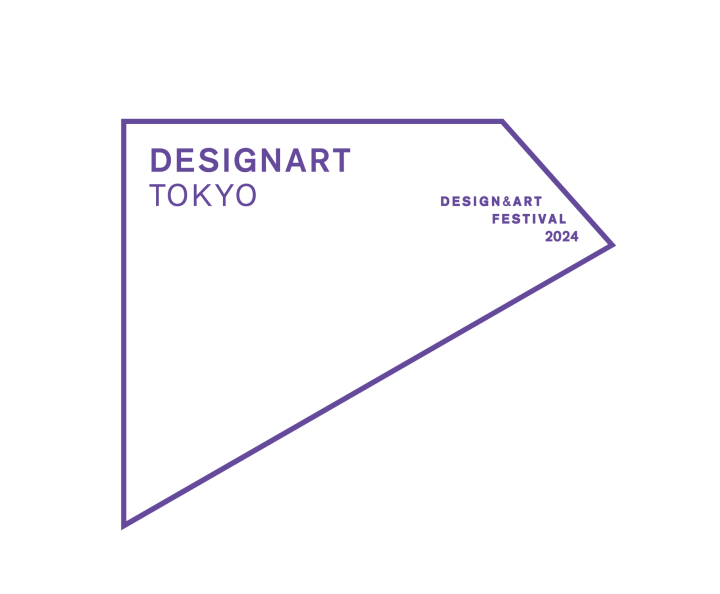「PF Chair」(2024)
日本のデザイン界では、長らく簡素でミニマルなスタイルが主流だったが、人の心に訴えかける情感あふれるものづくりを追求するデザイナーが、若手を中心に徐々に現れ始めている。プロダクトデザイナー/インダストリアルデザイナーの川本真也も、そうした新しい感性をもつひとりだ。オフィス家具メーカーのオカムラやRYOTA YOKOZEKI STUDIOで経験を積み、2024年に独立。以降、DESIGNART TOKYOやミラノのアルコバ、デザイン上海、インテリア ライフスタイルといった国内外の展示会に精力的に出展。そこで得た気づきや、今後の展望について話を聞いた。

「PF Light02」(2025)。円筒形のステンレスパイプに潰し加工を施して制作したLED照明器具。
携帯電話のデザインに興味を惹かれて
川本がデザインに興味を抱くきっかけとなったのは、携帯電話だった。2000年初頭の高校生の頃、膨大な数の携帯電話の新モデルが毎年各社から発売された。それらの製品の造形や機能に心を奪われ、このときに初めてデザイナーという職業を知った。
携帯電話のようなプロダクトデザインを学べる大学を目指して受験し、2013年に日本大学生産工学部創生デザイン学科に入学。その後、日本大学大学院藝術学研究科インダストリアルデザイン専攻に進学し、ハンディクリーナーや懐中電灯などの製品デザインを学んだ。

「PF Stool」(左)、「PF Sidetable」(2025)。ステンレスの鏡面仕上げと、塩浴着色処理加工を組み合わせたスツール(左)とサイドテーブル。
オカムラとRYOTA YOKOZEKI STUDIOで経験を積む
川本は当初、家電メーカーへの就職を考えていたが、大学の教授から「構造設計も含めた、幅広いデザインに携われるオフィス家具メーカーが向いているのではないか」と助言された。その言葉を受けて、オフィス家具や什器の製造・販売を行うオカムラのインターンシップに参加。そこでの体験に魅力を感じ、進路を変更。オカムラの採用試験を受けて合格した。
入社後、オフィスチェアを中心とした椅子のデザイン開発チームに3年ほど従事。以前から多様なプロダクトの開発に携わりたいという思いがあったため、異動を申し出て、什器や照明、公共家具などに取り組んだ。オカムラでの仕事はやりがいがあり充実していたが、将来のキャリアを見据えるなかで、次第に独立という選択肢を意識し始めるようになった。

「Folding Chair(フォールディングチェア)」オカムラ(2017)。Lives(ライブス)という家具シリーズの、座り心地を追求した軽快な4本脚のデザインの折りたたみ椅子。商品企画:中尾優衣、デザイン:川本真也、設計:北川匠里

「Carrera(キャレラ)」オカムラ(2019)。薄いパネル厚と細いフレームにより、空間をやさしく軽やかに仕切る間仕切り。商品企画:下村恒夫、デザイン:川本真也、設計:髙野和希
独立前にデザイン事務所で経験を積むことを考えて、プロダクトデザイナーの横関亮太率いるRYOTA YOKOZEKI STUDIOに、2022年に転職。家電、家具、日用品、化粧品の容器、中小企業のブランディングと幅広い分野のプロジェクトに携わる機会に恵まれ、多くの知見と経験を積むことができた。

「PF Chair」「PF Armchair」(2024)
企業の持つ素材や技術の魅力を生かす
2024年に独立。まずは自分の存在を知ってもらうことが重要だと考え、国内外の展示会に積極的に参加。2024年10月のDESIGNART TOKYOを皮切りに、2025年4月のミラノのアルコバ、6月にはデザイン上海と東京のインテリア ライフスタイルに出展した。
展示したのは、「PFS(Press Furniture Series)」という家具シリーズで、椅子、肘付き椅子、テーブル、スツール、サイドテーブル、そして、2種の照明器具の計7点からなる。これらは展示発表のためだけの作品ではなく、量産を視野に入れて輸送時および倉庫内の収納効率も考え、分解・組立可能な構造に設計した。

「PF Chair」(2024)。背もたれ、座面、脚部などを分解可能にした。
川本は日頃から各企業の持つ素材や技術に魅力や価値を感じており、このPFSシリーズにそれらを生かしたデザインを考えた。構造体には、金属や樹脂素材の加工技術に長けたフジアーチの協力を得て、円筒形のステンレスパイプの一部に潰し加工を施したり、鏡面加工を用いた。また、金属熱処理加工を専門とするメイネツの「塩浴着色処理」という特殊な技術を採用。それは酸化被膜を形成することで、素材の表情に変化を起こすというもの。メイネツとは国内の見本市で出会い、その技術や素材の表情に魅了され、いつか活用したいと考えていたという。


フジアーチによるPFS家具シリーズの制作風景(上記2点)。

メイネツの塩浴着色処理加工によって、「PF Chair」を制作している様子。職人の手仕事によって、唯一無二の模様と色味が生み出される。
国内外の展示会で反響を得る
国内外の展示会への出展を通じて、インテリアや建築の事務所、ショップやギャラリーなどから注目を集めてメディアでも紹介された。この一連の展示活動を振り返り、川本は次のように語った。
「自分が手がけた作品を、自らの手で世に発表するのは、PFSシリーズが初めての経験でした。作品が人種や言語、文化の垣根を越えて多くの方々から評価されたことは、私にとって大きな励みとなり、自信を深めるきっかけにつながりました。もともとは量産を前提に設計した家具でしたが、思いがけず海外のアートギャラリーの方から声をかけていただき、作品がアートとして受け止められたことに驚きと喜びを感じました。今後はアート作品のような表現的な創作にも、もっと取り組んでいきたいという思いが高まりました」。

「PF Table」(2024)。空間に軽やかさと洗練された印象をもたらすテーブル。潰し加工を施した円筒形ステンレスパイプを脚部に用いている。
2024年11月には、「marble2『金属織物、喜怒哀楽』」の展覧会に参加。これも企業の持つ素材や技術の価値を引き出すプロジェクトだった。大阪に本社をおくアサダメッシュでは、主にスマートフォンやタッチパネルなどのハイテク精密機器の製造に欠かせない極細線金属メッシュを製造・販売している。本展では、その製造過程で出る端材を活用し、デザイナーやアーティスト、フォトグラファーなど多彩なクリエイターが、それぞれの視点から作品を手がけた。
川本は「人の感情」をテーマに、アートワークのような作品を目指して2点制作した。オブジェ「廻廻嬉嬉」は、メッシュの端材を巻き重ねることで多様な形を生み出し、喜怒哀楽といった移ろいやすい人の感情の変化を表現。もう一方の作品「MATOI」は、人の感情が時に“オーラ”のように自然と周囲に伝わることに着目し、心の内面が透けて見えるようなメッシュの特性を生かしたテーブルを制作した。

「廻廻嬉嬉」(左)、「MATOI」(2024)。marble2出展作品。大阪・東京の2カ所で開催された。Photo by Kazuyuki Nagata(WACOH)
人の心に響くものを届けたいという想い
川本のウェブサイトには、ものづくりに対する明確な信念が示されており、クライアントの想いに寄り添う誠実な姿勢も伝わってくる。その核心にあるのは、「喜びと感動を呼び起こす製品、ブランド、サービスを(クライアントと)共にかたちにする」という想いだ。
「私にとって『感動』ということが活動の大きなテーマであり、人の心を動かすような製品を生み出したいという想いがあります。自分が『格好いい』とか、『美しい』と感じたものを、自分の視点やフィルターを通して形にし、それを見た人が『これ、いいね』と共感してくれる。そんな小さな共感が広がり、感動が人から人へと伝わっていく。そういう心に響くものをデザインという手段で人に届けたい。そして、クライアントの悩みや目指す方向を聞いて、それに寄り添ったデザインをしたいと考えています」。

2025年4月のミラノのアルコバにPFSシリーズを出展した際の展示風景。
活動を始めて1年余り。これからさまざまな挑戦が始まるなかで、手がけたいことを聞いた。
「プロダクトを中心にジャンルにこだわらず、幅広いものづくりに挑戦したいです。そのなかで、長く残るものをつくりたいという想いがあります。目まぐるしく製品が生まれる現代においても、時代を超えて使われ続ける、ロングライフの製品が存在します。私もそうした普遍的な価値を持つものをデザインし、後世に残すことを目標としています。それは文化や美意識を未来へつなげる行為でもあると考えていて、そういうものづくりに携わることが、デザイナーの使命でもあると感じています。一方で、もともと関心のあった家電は、生活と密接に関わるからこそ、多くの可能性があると感じています。ぜひチャレンジしたいプロダクトのひとつで、もし携わることができたら新たな価値を提案したいと考えています」。
今後も人の心を揺り動かし、日常に潤いと彩りを与えるものを生み出していってほしい。![]()

川本真也(かわもと・まさや)/プロダクトデザイナー、インダストリアルデザイナー。1990年神奈川県生まれ。2015年日本大学大学院藝術学研究科インダストリアルデザイン専攻を修了後、大手オフィス家具メーカーおよびデザイン事務所にて経験を積む。オフィス・公共施設の家具、家電、生活用品など多岐にわたるデザイン実績を持ち、2024年に独立。人と暮らしに寄り添う普遍的な製品づくりと、素材・技術・構造から新たな価値を導き出すアプローチで取り組む。