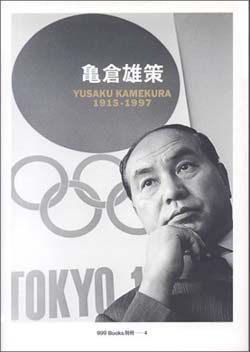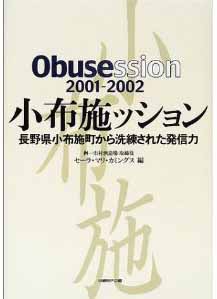
セーラ・マリ・カミングス 編 (日経BP企画・2,500円)
評者 深澤直人(デザイナー)
「日本人の心に火をつけた人」
小布施という町の名は以前からよく知っていた。長野県に6年間住んだことがあるので、栗菓子の美味しい店があることと、県内各地にあるその綺麗な店のイメージとして名前を覚えていた。1年ほど前、所用で須坂を訪れた際に、ちょっと足を伸ばして小布施に立ち寄った。千曲川と小高い山の間の小さな町並みがとてつもなく洗練されているのに唖然とした。こつ然と現れたその洗練された様に、「いったいなぜこの田舎が」という思いが浮かび上がった。京都や鎌倉のように歴史的な知名度が著しく高いわけでもなく、かつ古びたわびさびの世界とも少し違う。落ち着いていて綺麗でしかもスケール感もある。田園風景に溶け込んで、田舎なのに質のいい文化的な香りが漂っていた。
しばらくしてその訳がわかった。そこには単純に「まちおこし」という言葉では言い尽くせそうにない、それを築き、育て、静かに広めてきた人たちの存在と出会いと夢があった。今回紹介する本は、その小布施に花開いた文化活動「小布施ッション」を綴ったものである。その文化を深め、広めようと奮闘するひとりの外国人女性、セーラ・マリ・カミングスがこの「小布施ッション」の仕掛人である。彼女の夢は「人と人の繋がりで、小布施にいっぱい花を咲かせること」だった。田舎町の中心に美術館「北斎館」を建てたことで、人々の町並みへの意識が高まり、さらに栗菓子屋の竹風堂や櫻井甘精堂の出現や、セーラが取締役を務める桝一市村酒造場・小布施堂の社長、市村次夫を含む地権者5社の北斎館周辺の2万m2の町並みの再構築「町並み修景事業」によって、小布施は他に例を見ない「味わい空間」を生み出すことになる。
1994年に小布施堂に入社したセーラは周りからはどうやら「台風娘」と呼ばれていたようだ。確かにその略歴には、欧米人初の利酒師認定や桝一の再構築への取り組み、レストラン蔵部の開設、さらに日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2002大賞を受けるなど、その多才ぶりには驚く。セ−ラは言う「まちづくりとは人づくりのことです。そして人をつくるには、いろいろな世界、分野でさまざまな活躍をしている人と交わり、刺激を受けることが必要です。人々の交流は、テレビなどのマスメディアから一方通行的に情報を得ることではなく、人間同士が直接会話をすることから生まれます。ところが地方では、そのような機会はどうしても限られてしまいます。そこで2001年という新世紀のはじまりの年に、ひと月に一回『小布施ッション』と題した催しを開いていこうと決めました」。
この本には、毎月ゾロ目の日に開かれる集まりに招かれた12人の人たちの語りが収録されている。建築家、工芸家、落語家、デザイナー、歴史学者、脳科学者、社会学者、アーティストなどその顔ぶれは多彩である。興味深いスピーチとそこに集まった人たちの団欒、とびきり美味しい食事とお酒で夜は更けていく。語りの内容はさまざまだが、専門的な語り口ではない。対話するように穏やかでやさしい。ある特定の領域に興味のある専門家たちの集まりではないため、話はとてもわかりやすく、そして深い。その集まりに参加した人たちに様子を伺ったことがある。それは単に催しの企画ではなく小布施町の手厚いもてなしのようだ。
市村次夫はこのサロンを次のように語っている。「『小布施ッション』を支える思想は、平たくいうと『現代の旦那文化』です。そこに、メセナ、フィランソロフィーという都会的な概念とは違う、地方のゆったりした感触を感じていただけると幸いです」。
町をつくるということは単に建物や景観をつくることだけではないことが、この本を読んでいてよくわかる。そこに集まる人たちを幸せに、楽しくするために町の魂に息吹を吹き込むこと、そこでしか味わえない心地よい文化は、かたちだけでなく、営みによって築かれているに違いない。
「小布施ッション」は今年8月から2年目に入った。(AXIS100号/2002年11・12月より)
「書評・創造への繋がり」の今までの掲載分はこちら。