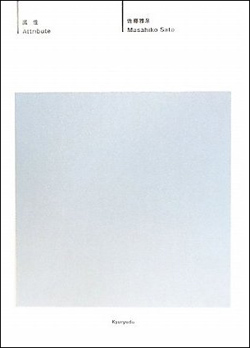REPORT | インテリア / ファッション / 見本市・展示会
2018.07.31 16:54
イッセイ ミヤケのミラノ旗艦店で開催された「My first me ー 自分にとっての初めての自分 ー」。表現研究者であり東京藝術大学大学院映像研究科教授の佐藤雅彦をディレクターに迎えた企画展は、3つの体験型インスタレーション作品と映像作品セレクションで構成された。
映像、アニメーション、グラフィックデザインの表現から脳科学の研究まで、分野を超えた佐藤の活動は、プレイステーションソフト「I.Q.」、NHK教育テレビ「ピタゴラスイッチ」といった代表作のほか、「計算の庭」(2007年、森美術館)や「これも自分と認めざるをえない展」(2010年、21_21 DESIGN SIGHT)など展覧会でも広く知られている。普段は意識をしない感覚を刺激し、日常に潜む発見に気づかされる作品の数々は、人々に驚きと楽しさを与えてきた。
本企画展はとりわけ“自分”に焦点があてられている。自分自身では当然、よく知っているつもりでいながら、実は認知していなかった“初めての自分”に出会う作品だ。

Photo by Valentina Sommariva
ショップ内の展示エリアに特設された3作品のうち「私は、あの人が見ている私を見ている」は、双眼鏡を覗いてみるという新作だ。店内のガラス越しに中庭の方向を眺める位置に置かれた1台の双眼鏡。覗き込むと、そこには、見えるはずの景色ではなく、どこからか見下ろされている自分の後ろ姿が現れる。明らかに誰かがこちらを見ていると思うのは、自分ではないまばたきによって、画面が暗くなる瞬間があるからだ。他人の目と脳を通過した自分の姿を初めて見て、戸惑い、驚き、場合によっては不安な気持ちにもなる。しかしその仕組みに気づくと、誰もが微笑んでしまうのだった。
周囲をキョロキョロと見回せばすぐに、ショップの1階から2階への階段の踊り場にある小さな窓から、双眼鏡でこちらを眺めている人物に気がつく。こちらが気がついたことを察知すると、その人は微笑んだり、手を振ったりしてみせてくれる。

この作品は、ミラノデザインウィークへの参加が決まった昨年の秋、イッセイ ミヤケのショップを下見に訪れた際に踊り場の小窓の存在を知って思いついたアイデアだという。場所の具体的な広さ、高さ、調光の具合、そして一番大切な雰囲気を佐藤は「トーン」と呼び、それらに見合った展示を考えるという。佐藤はこの新作について以下のように語る。
「カメラが別の場所に設置してあって、その映像が双眼鏡に映し出されるというのなら、今までにもよくある普通のアイデアだったでしょう。そうではなく、この作品では人が見ていることで演劇的な空間が生まれています。しかも、その人が何を思って自分を見ているのかは、わかりません。もし無人カメラだったら、監視目的のような意味がはっきりしてきますが、ここでは“私”を監視しているのか、クッキーを食べながらなんとなく眺めているだけなのか。つまり、人が介在するから幅が広くてわからなくなるのです。
もうひとつ、踊り場から見ている他人とのコミュニケーションも生み出しています。カメラだったならば、『ああ監視カメラがあそこにあるね』、と思って終わってしまいます。それ以上、仕組みを知ろうとはしません。でも人だとコミュニケーションが生まれます。『あれ?あなたが見ているの?』というように。僕はそれが大事だと考えています。表現のなかにコミュニケーションが生まれなければ、単なる展示のひとつでしかありません。人が介在したり、自分の指紋に愛着が生まれたり、といったコミュニケーションが生まれることが大切であって、それをつくり上げているということだと捉えています」。
愛着が生まれる「指紋」とは、もうひとつの作品「指紋の池」のこと。2010年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会で初出された作品だ。装置に指をのせると指紋がスキャンされ、他の多くの指紋が動き回る画面の中に放たれる。無数の指紋に紛れてしまう様は、社会の枠組みにいる自分を客観視するようでもあるが、もはやどれが自分の指紋なのかさえわからなくなる。

Photo by Valentina Sommariva
しかし、再び指を乗せると、「指紋の池」の中から自分の指紋が戻ってくる。その時に、生まれて初めて、自分の指紋に対する愛着や慈しみといった感情に気づく。「あなたにはこういう指紋がありますよ」と教訓めいたメッセージではなくて、この作品を通して自分を一度外に出してみることの試みがなされているのだ。


いまや指紋認証や顔認証などの認証技術や人工知能の発展によって、自分自身よりも社会のほうが個人の属性を情報として取得し、照合しはじめている。自分がいちばん理解していると思い込んでいるだけで、もしかしたら社会の方が正確に、そして多くの情報を持っているかもしれないと示唆するような作品でもある。
そしてもうひとつの体験型作品「ブランコを指で乗ろう」では、また違った初体験を来場者に促した。小さなブランコに指を置いて揺らしながら、目では、ゆらゆらと揺れる映像を見ていると、体性感覚情報によって、そのふたつの情報が脳で合成される。その結果として、指でブランコに乗っている状態を自覚するのだ。この時、指でブランコに乗った自分は、「初めての自分」になる。

Photo by Valentina Sommariva
こうしたインスタレーション型作品はいずれも、覗き込んだり指を乗せたり、といった見る側からの行動によって未知の感覚を知ることができるものだ。その点でも、ミラノデザインウィーク期間中に多い新作家具のインスタレーション展示とは大きく異なる。見たままの形や機能性を伝えるためのインスタレーションではなく、すべて鑑賞者の内面に起きることが中心にある。初めて見るもの、しかも自分の中に働きかけてくるものについて佐藤は次のように話す。
「表現は外に現れるものを指しますが、この展示で表面に現れているのはとても静かなものです。ところが体験するとしないのとでは大違いで、一旦それを体験すると、自分の中に確かに響いてくるんですね。今回、ミラノでは特に日本で展示をした時とは全く違う反応に、直に触れることができました。指紋が池に放たれたときの驚き、そして指紋が戻ってきたときの驚き……。内面まで入り込み、心の奥深いところをぎゅっと抑えられたような表情を目の当たりにして、まだ作品としてこれから考える要素が含まれていると気づきました」。
双眼鏡やブランコについても、なぜ思いついたアイデアをつくりたくなったのか、なぜ鑑賞者がこんなにも驚き、喜んだのかを繰り返し考えながら、次の作品に結びつけていくのだという。
イッセイ ミヤケのショップ内での展示は、三宅一生の強い希望だったそうだ。「以前、21_21 DESIGN SIGHTで展覧会をすることが決まった時に、『佐藤さんは全部わかって作品にしているけれど、そうではなく、佐藤さん自身がまだ解決していない、誰もわからないことをやってほしい』と三宅さんに言われました。いまはその言葉がとてもよくわかります。すでに発見したものを体裁よく、格好良くつくり上げるのではなくて、つくって、見つけてほしいということでしょう。21_21 DESIGN SIGHTだけでなく、ミラノの旗艦店という大事な場所に若手を置いて、世界に紹介しようとしてくださっている。それに応えなくては、と。僕は少しばかり三宅さんに恩返ししたかったのだと思います。多くの人が訪れるこの場所は、新しいことを発信する強い意思があることを、伝えたいと思ったんです。ここではなにか新しくておもしろいことをやっている、最先端のギリギリの、ビリビリくるほど危ういことをやっているぞと伝えたかったんですね。それが、三宅一生さんとイッセイ ミヤケへの少しばかりの恩返しになっていれば嬉しいです」。

Photo by Valentina Sommariva
「一枚の布」をコンセプトに、国籍や国境の概念を超えた衣服を生み出し、デザインを通して常に新しい可能性を探求してきたイッセイ ミヤケ。本展は、新作コレクションとは直接結びつかないにも関わらず、発想の意外性や驚き、未知の感覚を刺激する点で、その世界観にぴたりと重なるだろう。
家具やインテリア製品だけではなく、人の心を揺さぶるデザインが話題性をもって受け入れられるこうした側面も、ミラノデザインウィークの魅力のひとつである。![]()