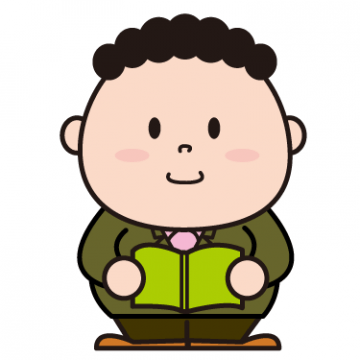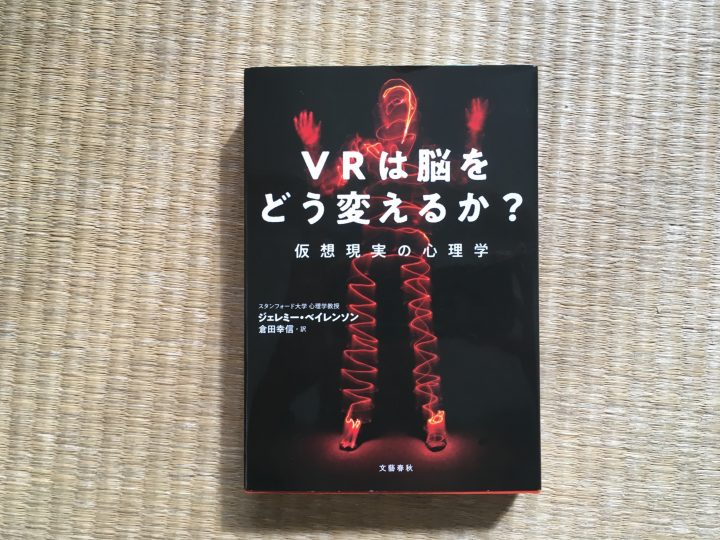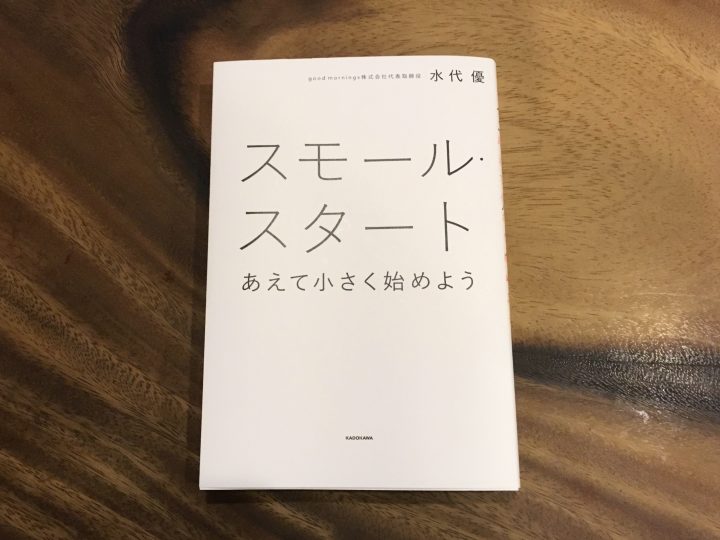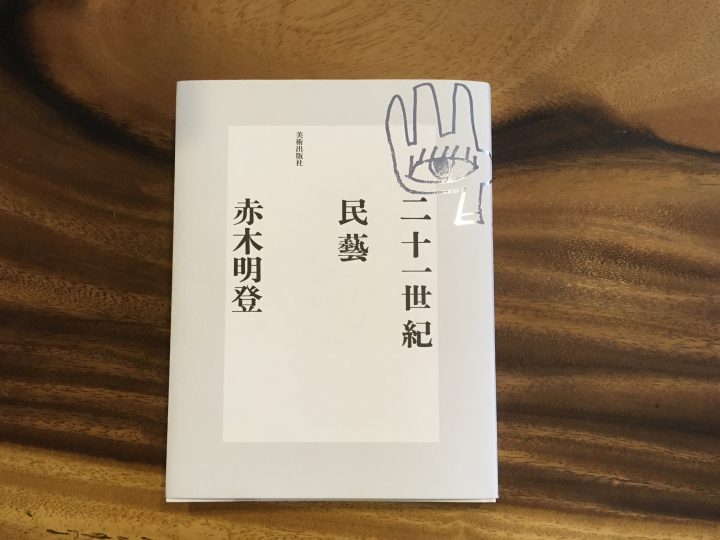たぶん2010年代に入ったあたりからだと思うけれど、東京の食のシーンが明らかに変わったと感じた。単なる流行の変化というのではなく(そういう変遷なら昔から繰り返されてきた)、それは「潮目が変わった」とでも言うような、もっと本質的な変化だったと思う。
まず若い料理人たちの店が増えた。景気が良かった頃はパトロンが別にいて、若く才能のある料理人に店を任せることも珍しくなかったが、そういう店は豪華な内装が料理人の身の丈とあっていないことも多く、なんだか居心地が悪かったのを覚えている。一方、新世代の料理人たちの店は自分たちで立ち上げた店だ。こぢんまりとしているけれど、無理に背伸びをしない自然体のスタンスが清々しい。いつの間にか彼らの店に足を運ぶことが多くなった。
食材はよく吟味され、作り手の顔が見える安全なものを仕入れるのはもちろん、もっと美味しくするための仕込みの手間も惜しまない。それでいて価格はリーズナブル。そんな志の高い店がある時、続々と誕生したのだ。
店の雰囲気や料理だけでなく、彼ら新世代の料理人には、もうひとつ共通点があった。彼らの店に通いながら漠然と感じていたことを、文筆家の井川直子さんが、「変わらない店 僕らが尊敬する昭和 東京編」で的確に表現してくれている。
「もう数年も前から、私より若い料理人やソムリエやコーヒー焙煎師たちが、昭和の店の話をキラキラとした目で語ることがたびたびあった」
井川さんは本書をこんな言葉で始めているのだが、読み始めた瞬間に「そうか!」と思った。若い料理人はみな勉強熱心で、休みの日にはあちこちの店を食べ歩く。そんな中、彼らがこぞって「あそこ素晴らしいですよね!」と称賛するお店があった。たとえば三田のフレンチ「コート・ドール」。あるいは湯島の居酒屋「シンスケ」。もちろんそれぞれに素晴らしいお店だが、それらを「昭和」というキーワードで串刺しにしてみると、途端に見えてくるものがある。
「昭和」と聞くと、懐かしさやノスタルジーを連想する人もいるかもしれないし、戦後の激動期を生き抜いてきた人の中には「それほど良い時代じゃなかった」という人だっているかもしれない。ただ、ここで大切なポイントは、若い料理人たちはその時代を知らないということだ。彼らにとって「昭和」は、新しい時代との出会いだ。だとするなら、彼らは「昭和」という時代に何を見出しているのだろうか。おそらくそこには、次の時代を創っていくために必要なヒントがあるはずだ。
ひとつだけ本書の中からご紹介しよう。
原宿に「重よし」という日本料理の名店がある。オープンは昭和47年。店主の佐藤憲三さんは東京を代表する料理人のひとりだ。佐藤さんの料理に多大な影響を受けているのは、恵比寿で個性的なイタリアンを提供する若きオーナーシェフ。ある日、彼は重よしで出されたすっぽんのスープに驚かされたという。なぜならそのスープには具がまったく入っていなかったからだ。スープだけなのに強烈にすっぽんを感じさせ、数日後、気がつけばまたあのスープを飲みたくて堪らなくなっている自分がいた。
本書で、このすっぽんスープがどのように生み出されたかが明かされているが、臭み消しの生姜などを使わずにクリアなスープを作るにはどうすればいいか、あらゆる条件を微細に変えながら、ただひたすら作っては味を確かめることを繰り返し、一年かかってようやくどうすればいいかわかったという。
「正しく、丁寧に。料理はこれしかないんですね。正しくとは(習ったとおりという意味でなく)古典的な基礎のこと。それをひたすら愚直に。おそらく一番大切なことです」
自らの手を動かすことでつかみとられた真理。本書を読んでいると、こういった金言にあちこちで出会うことができる。重よしでは鰹節はその都度掻き、練り胡麻も根気よく擂り鉢であたる。出来合いのものを使わないのは、千人に一人でも違いがわかるお客さんがいるからだという。佐藤さんはそのたった一人をイメージして料理をつくっているのだ。この姿勢が、若い料理人の心をとらえて離さない。
井川さんが取材をした昭和の店の人々は、「日々するべきことをしてきただけ」とみな淡々としていたという。にもかかわらず彼らの言葉が、ぼくらの心を揺さぶるのはなぜだろう?おそらくそれは、彼らの仕事の中に他者に対する敬意があるからではないだろうか。
井川さんは別の本(『昭和の店に惹かれる理由』)の中で、ある老舗モツ鍋屋を取材した時のことを書いている。その店では新鮮なモツをなんども徹底的に洗う。なぜそこまでするのか、と訊きながら、臭みをとるためだという答えを予期していた井川さんに対し、その店の女将はあたりまえのようにこう言ったという。「人さまの口に入るものだからですよ」
この女将と重よしの佐藤さん、ふたりの仕事の根底には、他者への敬意がある。
世間では声の大きな人ほど注目を浴びやすい。SNSを覗けば、他人への敬意のかけらもない攻撃的な言葉で溢れている。でも決して声高には語らないけれど、長い人生の中で、淡々と自分の仕事と向き合ってきた人たちもいる。本書はそういう人々の宝物のような言葉をぼくたちに届けてくれる一冊だ。
仕事で迷っている人にこそぜひ手にとってみてほしい。この本の中には、きっとあなたの心に届く言葉があるはずだ。![]()