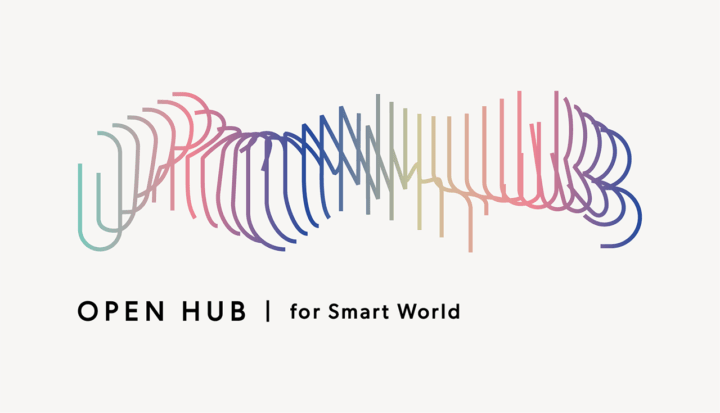PROMOTION | テクノロジー / 展覧会
2023.02.17 18:49
NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で企画展「多層世界とリアリティのよりどころ」(会期:2022年12月17日〜2023年3月5日)が開催されている。
メタバースやミラーワールドといった仮想空間が社会に実装されつつある今、リアルとバーチャルの「はざま」に無数のレイヤー(層)が生み出されている。多層世界での人々の暮らし、文化や考え方はどのように変化していくのか?
展示会場をデザインした東京大学生産技術研究所特任教授/建築家の豊田啓介さんとICC主任学芸員の畠中 実さんに尋ねた。

Photo by Nishida Kaori
以前と違う解像度で世界を見ている
——ICCでは「多層世界」からインスパイアされる表現を、2020年から継続的に取り上げています。豊田さんは最初からこの「多層世界」シリーズに関わっておられますね。
豊田啓介(以下、豊田) はい。いま目の前に全3回分のフライヤーを並べてもらっていますが、こうしてあらためて見ると、第1回(「多層世界の中のもう一つのミュージアム」)はかなり要素をつめ込んだビジュアルですね。第2回(「多層世界の歩き方」)はすこし整理されてきて、今回は白を基調に、非常にすっきりしたものになっています。
これは偶然だとは思いますが、初めはバーチャル体験に焦点が当たっていたものが、回を重ねて、リアル側の体験を豊かにすることにシフトしてきたのかもしれません。それは「バーチャルだけじゃなくて、やっぱりリアルも大事だよね」という社会の感覚の変化をトレースしているように感じます。
でもそれは決して物理世界に回帰しているわけではなく、「多層世界」についての考え方が3年というスパンをかけて1周したことで、僕たちはいま、以前と異なる解像度で物理世界を見るようになっているのだと思います。そのことを面白く感じますし、僕自身のスタンスもそれに近いです。

豊田啓介(とよだ けいすけ)
東京大学 生産技術研究所 特任教授/建築家(NOIZ、gluon)。
アプリ「ヴァーチュアル初台」とハイパーICC※の制作を監修。「多層世界」シリーズでは、第1回から設計監修を担当する。

2020年から開催されてきたICCの企画展「多層世界」シリーズのフライヤー。
社会の感覚の変化をトレースしているように、ビジュアルがすっきりしたものになった。
デザイン:寺井恵司
※ハイパーICC:3DスキャンによってICCの拠点である東京・初台の一街区を点群データに変換し、ゲームエンジンを用いて「ヴァーチュアル初台」として再構成。その中にあるハイパーICCは、仮想空間の中のもうひとつのICCとなるオンライン・プラットフォームと位置づけられている。ICCで開催された展示・イベントを立方体ボックスで表し、仮想空間における新たな建築・ミュージアムの可能性を追求する。
畠中実(以下、畠中) 確かに最初の年はハイパーICCをオープンした年でもあり、現実の会場とバーチャル会場の連携について、まだ方法論を模索する部分がありました。
2年目は、テーマを隔離期間中の過ごし方に移し、多層的な世界をどのように「歩く」のかという点に注目しました。そうした取り組みを経て、いま最も強く感じていることは、もはや「リアル」と「バーチャル」を2極化させたかたちでは捉えられなくなってきている。むしろその2極の間で「どのへんが自分の生きやすいリアルなのだろう」「どのレイヤーだとより良い過ごし方ができるだろう」といった、それぞれが居心地の良いバランスの取り方を探している。これから社会はそのような方向に進んでいくのではないか——という考えのもとで本展を企画しました。

畠中 実(はたなか みのる)
ICC主任学芸員。1996年の開館準備からICCに携わり、多数の企画展を担当。「多層世界」シリーズでは、キュレーションを担当する。
リアリティとは何かを問い直す
——従来であれば「自分にとって、リアルとは何か?」をわざわざ問う必要はなかったが、メタバースやデジタルツインが社会に実装されるなか、「リアリティ」の捉え方が人それぞれ変わりつつあるということでしょうか?
豊田 そうですね。どうしても「リアル」の対に「バーチャル」があるというイメージがされやすいのですが、それらは二項対立なのではない。その間にはグラデーションがあることを認識したうえで「リアル」を眺めてみると、個人個人で微妙に色合いが異なることに気づくはずです。
たとえば、建築や土木の業界で3D技術で空間を記述する場合、その方法は「絶対記述系」なんです。世界をすべて厳密に記述していく。それに対して、ゲームエンジンの空間記述の仕方は、「観測者視点」なんですね。観測者の周囲は概ね正確に記述しているけれども、距離に応じて記述の精度は落ちていきます。
どちらがいいかということではなく、同じ世界に複数のプレイヤーが同時に参加するような場合、絶対記述系の空間把握の方法ではデータが膨大すぎて、ハレーションを起こしてしまいます。だから、ゲームエンジンでは観測者視点の空間記述の仕方が採用されているわけです。そこには同じ世界であっても観測者ごとに多少のズレがあります。
観測者ごとの「ズレ」は、現実世界で言えば、一人ひとりの現実認識の仕方の違いであって、この「世界の認識方法はみんな異なる」という事実が、社会全体を円滑化させている要素だと思うんです。

最初はシリーズ化することを意図していなかったが、気づけばシリーズとなっていたと畠中さんは振り返る。
畠中 バーチャルを経由したリアルはそれ以前の「リアル」とは違っているはずです。バーチャルという存在ができたことで、逆に「あなたにとってのリアルとはなんですか?」と問い直す必要が出てきた。正確に言えば、「どのレイヤーがあなたにとってのリアルですか?」と聞いたほうがいいかもしれない。
コンピュータは発明当初から意識を拡張する装置だと長く言われてきましたが、レイヤー化した世界がプラットフォームになってきて、ようやく本当の意味で人間の意識が拡張されはじめたと思います。むしろこういうあり方でしか僕らは変われないんじゃないかな。
人々の意識が拡張された世界のリアリティは、どれもパラレルに存在している世界であって、私としては、アートがそうした社会の変化を何よりも先んじて表現していると感じます。アーティストは、炭鉱におけるカナリアのような存在だとよく言われるところですね。
豊田 そうですね。グラデーショナルな選択肢としてリアルだけを選んでもいいし、バーチャルだけを選んでもいいわけですが、その二つの混ぜ方にこそ、これからの新しい価値があるのではないでしょうか。
次元をまたいだ表現にある面白さ
——本展で特に印象に残った作品を教えてください。
豊田 柴田まおさんの『Blue』という作品は面白いと思いました。彫刻家が彫刻をメディアアートを通して表現すると、「消す」という方向にもっていくのは驚きました。モノがモノであることを否定しようとしているように思います。
実は、本展の会場デザインを考えたとき、会場全体を緑にして、全部クロマキー合成してみようかと思ったんです。でもすでにこの作品に先取りされていました。「やられた」と思いましたね(笑)。

会場風景。画面右が「Blue」 柴田まお。
会場に設置されたカメラを通して見ると、青い彫刻はすべて消えたように見える。
Photo by Kioku Keizo 写真提供 NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
畠中 内田聖良さんの『バーチャル供養講』は、3Dスキャンされた思い出の品が仮想空間に「奉納」されていて、それをVRで体験する作品です。バーチャル空間は、インタラクティブな作品と親和性が高く、同時に、デジタルアーカイブ的な方法論ともつながっています。
作者はこの「思い出の品」を3Dスキャンしたうえで、そのデータを誰でも使えるアセットとして公開しています。インタラクティブな作品でありつつ、アーカイブという視点でのアーキテクチャ・デザインとしての考え方も含まれていて、テーマ自体にも多層性があるといえるかもしれません。
アーカイブ性という点では、豊田さんたちが各地の名建築を3Dデジタルアーカイブしている取り組みにも通じますね。
豊田 まったくそのとおりです。これまでのアートって、メディウム(媒体)がモノだったわけで、2次元の絵画、3次元の彫刻など、どうしてもカテゴリーが分けられていたわけです。それがメタバースやデジタルツインなどの技術によって、複数のメディウムと次元をミックスし、さまざまな次元をいろいろな組み合わせで選択できるようになったことで、次元をまたいだ表現が可能になっている。そこにいまのメディアアートの面白さがあるのでしょうね。
関連して、空間デザイナー、ファッションデザイナー、建築家、あるいは音楽家など、これまで重なることのなかったプロフェッションがさまざまな場面でオーバーラップすることが増えています。建築の分野にいる僕は、それが劇的な速さで進んでいると実感しています。

内田聖良の「バーチャル供養講」を体験する豊田さん。
VRゴーグルをかけると、バーチャル空間上に「奉納」された作者の思い出の品にふれることができる。
境界線が曖昧になっていくなかで
畠中 絵画や彫刻、音楽といった領域は職能として線引きされていましたが、いまはどんどん拡張している。従来の専門性を持った役割がオーバーラップする現象が起きています。極を持たず、どれだけ遍在性を持つのかという意味を表すICCの館名「インターコミュニケーション・センター」に時代が追いついたではないでしょうか。特に初期のメディアアートは、さまざまな職能の専門家によるコラボレイティブな作品が多かったですが、いまはそれぞれの職能が重なっていると実感します。
それを表現するために、今回の会場デザインでも、作品と作品の間に壁を設けないようにお願いしました。天井に配置された曲線の照明が作品をゆるやかに束ねていて、統合しているように感じます。ランダムな大きさや高さ、重なり合う曲線が、作品のオーバーラップやレイヤー化された世界が示唆されているようにも見えて、面白い空間デザインだと思います。
豊田 本当は壁をつくらせてもらったほうが会場デザインとしてインパクトを与えやすいですが、壁を設けず、かつ「リアル」と「バーチャル」の概念を会場デザインに落とし込むのは難しかったです。

会場の上に設けられたLED照明がそれぞれの作品空間を表す。
——美術館の役割を含め、これからの「多層世界」とアートはどのように変化していきますか?
豊田 リアルとバーチャルだけではなくて、従来は二項対立だと思われていたものの境界線が、これからはどんどん曖昧になっていくと思うんですね。美術館は、そのはざまでの変化を起こし続ける存在、展示だけでなく制作や、もっと直接的な関与の仕方も含めて、アートのエコシステムをつくる存在、プラットフォーム的な存在になっていかざるを得ないのだと思います。そういうシステムづくりの可能性は僕も探ってみたいし、関わっていきたいですね。
畠中 「バーチャル供養講」のように、ある作品が作品だけをもって完結するのではなくて、SNSの中で広がっていく、そのことも含めてひとつの作品であるというあり方は今後増えていくでしょう。ICCとしても先進的で考えさせるメディアアートを引き続き、取り上げていきたいと思っています。![]()







![NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]にて 「多層世界とリアリティのよりどころ」展が開催](https://www.axismag.jp/axismag-admin/wp-content/uploads/2023/02/MG_0396-720x480.jpg)