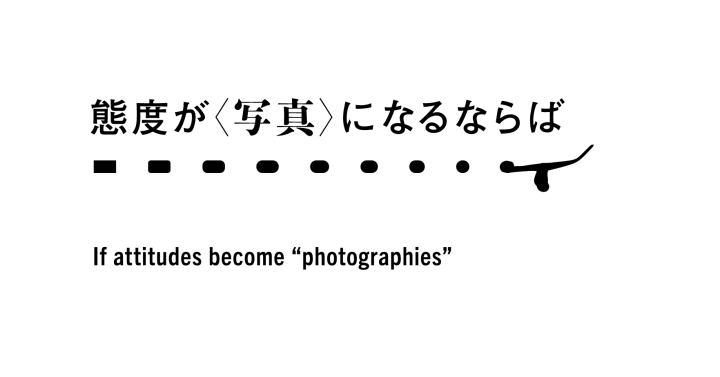INSIGHT | ソーシャル
2023.12.01 15:17

1990年代にイギリスで生まれ、近年さまざまなプロジェクトやプロダクトを生み出している「インクルーシブデザイン」という手法。ユニバーサルデザインへの反省を含んでいるというこの方法論は、多様な視点や意見をデザインや開発の「上流」に取り入れることで、まだ見ぬ未来を創造する。ソニーが開発した「XRキャッチボール」は、その新たな事例のひとつだ。取り組みの内容を取材した。
「XRキャッチボール」とは
ボールを使わないキャッチボール。ソニーグループのインハウスデザインチームであるクリエイティブセンターが開発した「XRキャッチボール」は、スマートフォンを持ったふたりが仮想のボールを投げ合う遊びだ。
ひとりが振りかぶって仮想のボールを投げると、相手との間に置かれたスピーカーから「ピッピッピッ」と電子音が3回鳴る。徐々に近づいてくる電子音のリズムに合わせて相手がスマートフォンのボタンを操作すると、ボールをキャッチすることができる。電子音の間隔は強く振りかぶると短く、ゆっくり投げると長く、というように加速度に応じて変化し、それによってボールのスピードを認識できる。また、キャッチする瞬間にはスマートフォンが振動し、数種類の効果音がキャッチの良し悪しを伝えてくれる。

XRキャッチボールを体験する中川テルヒロ。「息子からは『もしパパの目が見えたら』と言われることもある。キャッチボールは諦めたことのひとつだったけれど、XRキャッチボールはその楽しさを思い出させてくれた」と語る。
現実世界と仮想空間を融合したこの「XRキャッチボール」は、「息子とキャッチボールをしてみたい」という視覚障害の当事者で一般社団法人「PLAYERS」理事を務める中川テルヒロの声から生まれたものだ。音の情報や振動を頼りにキャッチボールが可能になるため、視覚障害のある人、さらには腕を大きく動かすことのできない高齢者や身体の不自由な人も楽しむことができる。
また、「窓」と名付けられたテレプレゼンスシステムを通じてオンライン環境に接続し、遠隔地にいる相手と遊ぶことも可能だ。東京・銀座の実験的ポップアップスペース「ソニーパーク・ミニ」で7月に開催された「パークラボ EXPT.07 キャッチボールは遊びの垣根を超えるのか?」や10月に幕張メッセで開催された「CEATEC 2023」では、別のショールームに置かれた「窓」を介して、多くの人がこのボールを使わないキャッチボールを遠隔で体験した。

画面の向こう側にいる相手とも、会話しながらキャッチボールを楽しむことができる。プロダクトデザインを担ったクリエイティブセンターの唐澤才(画面)がデモンストレーションをして見せてくれた。
「開発のきっかけは、視覚や聴覚に障害がある方たちと実施した2021年7月のワークショップでした。インクルーシブデザインの手法によって何か新しい価値を生み出せないかと企画したワークショップで、お招きした中川さんに『目が見えなくなって諦めたことはありますか』と尋ねたところ、キャッチボールという答えが返ってきたことから始まりました」。UI/UXのデザインを担った、同社クリエイティブセンターのデザインプロデューサー、反畑一平は、開発の経緯をそう振り返る。

開発を担当した反畑一平(写真中央)。反畑は「キャッチボールをXR化することは、チャレンジングだが挑戦する価値があると感じた」と話す。
従来は「除外」されてきた意見を
インクルーシブデザインとは、従来の製品・サービスのユーザーとしては除外(Exclude)されていたさまざまな人々を、企画や開発のスタート段階から包摂し(Include)、ともに考えていくデザインの手法。その世界的権威であるロンドン芸術大学客員教授のジュリア・カセムは、かつてAXISの取材(vol.223)で、インクルーシブデザインについて「単に誰もが使いやすいものをデザインするということではありません」と語っている。
よく比較されるユニバーサルデザインは「誰にでも公平に利用できること」など7つの原則に基づいて、製品やサービスのデザインに「体の不自由な人、障害のある人も使いやすい」という視点を取り入れる手法である。しかし一方で、障害のある側は「参考意見」を述べるにとどまり、製品開発やデザインのスタートから関わることは少なかった。

UI/UXだけではなく、スマホカバーなどの物理的なデザインも改良が重ねられた。「どんな手の大きさでも握りやすい形状にすることはもちろん、テスト段階では子どもたちの手からスマホが離れてしまうことがあったので、その点も考慮した」(反畑)。
これに対してインクルーシブデザインは、これまで「ターゲット」とされてこなかったユーザー(必ずしも障害者とは限らない)の意見や視点を、製品開発の初期段階から取り入れ、巻き込み、ともに検討することで、従来はなかった新たな価値や提案を生み出そうとする手法。手を動かしにくい/動かない、耳が聞こえにくい/聞こえない、目が見えにくい/見えない、コミュニケーションが苦手、あるいはLGBTQといった人々のさまざまな不便さや課題を解決するためのデザイン手法であり、生み出されるプロダクトやサービスは必ずしも万人向けにはならないこともある。
それでもこの手法は、健常者が気づかないような潜在的ニーズを発見し、多くの人々に訴求しうるデザインを実現する可能性を秘める。カセム教授は「プロセスがインクルーシブであれば、柔軟なつくり方ができるのです。多様なステイクホルダーを巻き込むインクルーシブデザインという領域は“大きな傘”であり、その下に参加型デザインやソーシャルデザイン、社会イノベーションなどの言葉が含まれています」(AXIS vol.199)と、その手法が包含する領域の広さを強調する。

中川は、デバイスの改良を繰り返すチームの「思いと情熱にまず感動した」と話す。
誰もが新たな価値を生み出し得る存在
「『息子とキャッチボールをしてみたい』という中川さんの話を受けて、正直『難しい』と感じました。だからこそチャレンジしてみる価値があると思い、デザインやR&Dのメンバーを交えて話し合いを進めました」。コロナ禍のなか、開発に着手した反畑らのチームがまず考えたことは、「そもそも人はキャッチボールのどの部分に面白さを感じているのか」ということだったという。
ボールを投げるとき、受けるときの緊張感。相手がボールを捕ってホッとする安心感。ボールが往復するリズム。その間の会話。チームでは、それらが「楽しさの秘訣」なのではないかという仮説が立てられた。単に誰もが使いやすいグローブなどをデザインするのではなく、キャッチボールという行為の本質を問い直したうえで、キャッチボールで得られる”体験そのもの”をデザインした結果が、「XRキャッチボール」なのだ。
反畑は、従来のデザインプロセスを肯定的に捉えつつも、「(意見を)聞きたい人にしか聞いていなかった」と振り返る。「すべての製品には、『最初のひとつ』があるわけです。われわれはそこに新しい価値を常に求めているけれども、見えているつもりで見えていないこと、聞いているつもりで聞いていないことがあるのではないかという疑問から、この開発はスタートしました。これまで接したことのない視点に出発点を置いたことで、本質的な問いを立てることができたし、それがこれまでにない『最初のひとつ』につながったと思う」。

障害のありなしが重要なのではなく、さまざまな視点や意見を包摂する過程が重要なのであり、そこに新たな価値創造の可能性があるのではと、反畑は言葉を継ぐ。ソニーは、2025年度までに原則すべての商品やサービスの開発過程において、障害者や高齢者らの意見を聞き、インクルーシブデザインの手法を取り入れることを目指している。国内企業では先駆的な取り組みとなる。
このような取り組みは同社のなかでさまざまな動きを生み出しつつある。ソニー・インタラクティブエンタテインメントとソニーセミコンダクタソリューションズ、ソニーグループの3社は、ソニー・ライフケアグループと協力して、高齢者のリハビリに対する新たなアプローチを導入している。開発したのは、リハビリ用ゲーム「キノコビト」(写真下)。人の手がコントローラーの役目を果たし、身体の動きとインタラクティブエンタテインメントを組み合わせた、「ゲームによるリハビリ」を試験的にスタートさせた。

画面上から落ちてくるキャラクターをキノコの上に乗せるゲーム、「キノコビト」。人の存在や動きを認識するセンサーカメラによって、コントローラーなしでプレイするスタイルが可能になっている。
徐々に視力を失ったという中川は、「XRキャッチボール」を体験して「高校生のころを思い出した」と笑顔で語る。人間は、本来的に誰もが何かの「マイノリティ」だ。カセム教授が「シナリオの革新」と語るこのプロセスは、旧来のデザインの前提——新たな製品やサービスは健常者/マジョリティが設計するものであり、障害者/マイノリティは手を差し伸べるべき存在——に対して、誰もが社会に変革をもたらし得ること、新たな価値を生み出し得る存在であることを強く思い出させてくれる。(文/安藤智郎、写真/宇田川俊之)![]()

XRキャッチボールの開発に携わったクリエイティブセンターの(左から)西原幸子、反畑一平、PLAYERSの中川テルヒロ、PLAYWORKSのタキザワケイタ。

「キノコビト」の開発を進めるクリエイティブセンターの(左から)江下就介、高木悟郎、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの奥村泰史。