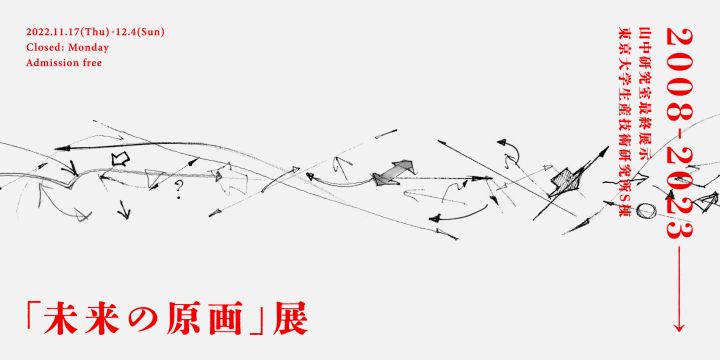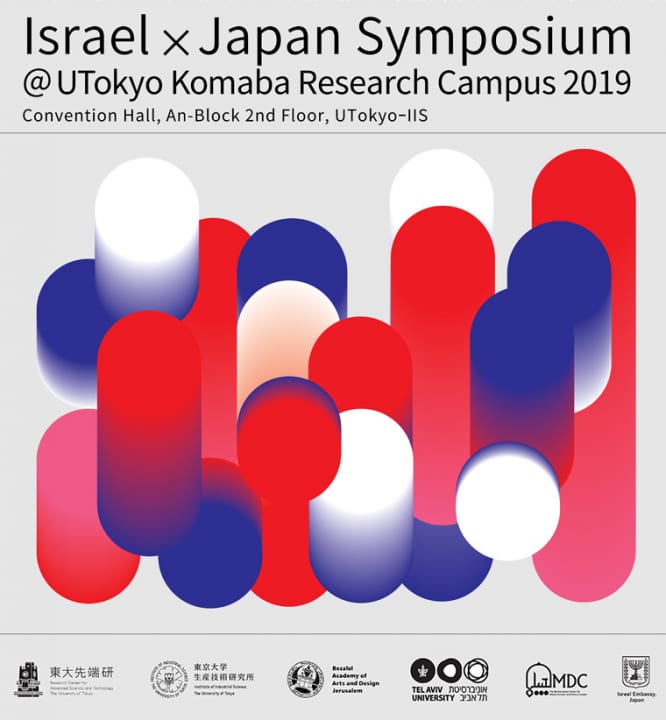東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。
東京大学 特別教授 山中俊治さん
「自らのコアを見つけ、こだわり、拡げていく」
デザイナーとして幅広い製品をデザインする一方、ロボティクスなど先端技術にも関わり、多様な領域を跨ぎながら活動を続けてきた山中俊治さん。いかにしてデザイナーという肩書きを超えてきたのか。東京大学生産技術研究所の研究室にうかがった。
自らが“何か”であろうとしない
――さまざまな領域を超えて活動されていますが、山中さんの中でいちばんしっくりくる肩書きは何でしょう?
ないですね(笑)。でも、ないことがいいんだと思っています。いろいろな肩書きを付けて、カテゴライズしてフレーミングするのはとても効率が良い。なぜなら、それだけやっていればいいから。でも、それを決めなかったおかげで、今の僕があると思っています。「デザインの最高賞(2004年毎日デザイン賞受賞)をいただいたときに、自分はデザイナーと認識されたんだな」と思ったぐらい。そんな感じで、何かであろうとしないほうがいいのでは、と思うんです。
――デザインを学ぶ人たちにメッセージを送るとするなら、「とらわれないこと」が大事だと?
そうなりますね。しかし、コアとなるものは必要です。つまり自分が最もワクワクすること。それを見つけたなら、とことんこだわってほしい。僕にとっては、人とマシンが一体化するときの精妙でフェティッシュな領域が最もワクワクすることで、コアの部分なんです。自分の美意識あるいはこだわりと言ってもいい。みなさんにもそれを見つけてほしい。自分のコアがない仕事に就くことがあるかもしれないけれど、コアからどんどん離れていくと感じたのなら、その仕事を続けないほうがいいと思います。

ロボット「サイクロプス」
――山中さんのコアの部分という意味では、ロボット「サイクロプス」は、機能的には人の動きを視線で追うというシンプルなものですが、コードなどのかっこいい意匠にはかなりのこだわりがあったと感じます。
そう言ってくれると嬉しいですね。実は「サイクロプス」は自分がつくったなかで最高のもののひとつだと思っています。あれは、自分がさまざまなロボットを見て、「あ、生きているみたいだ」と思える瞬間を抽出したものなんです。「視線」を持っているというのは認知の表象であり、脊椎という柔軟構造を持つことは生命体の進化のある意味頂点の部分だと思っています。そうした「人らしさ」のエレメントを抽出して、空気圧チューブというある種プリミティブな仕掛けで動かす。それらを上手に配置すると、とてもフェティッシュでいい感じの人工生命らしさが表れる。それが「サイクロプス」の本質であり、開発理念でもあるんです。
――あらゆる思考において、「とらわれないこと」がキーワードとなりますか?
それはとても意識しています。常に場所や専門性にとらわれない領域にいたい。スケッチワークにはとらわれているかもしれないけれど。

自分を閉じ込めてはいけない
――昨今、デザインという言葉が幅広く使われるようになっていますが、長年デザインに取り組んできた立場として、デザインとはどういうものだと考えていますか。
自分の根幹に触れるために、それに対して誰かが共感してくれるためにデザインをやってきました。それをデザインと呼ぶなら、それでいいし、みんなにももっとデザインをしてほしい。ただし、プロとしてという話になると、デザインの定義が必要で難しくなる。わかりやすく言うなら、見る人、使う人にきちんと共感してもらうための対話や実験を怠らないこと。それができればいちばんハッピーだと思います。未来の人間は、そこしかAIに勝てないんじゃないかな?
――以前、Xのツィートで、教授の求める「正しい研究成果」をそのまま自己評価にしてしまい、「良いもの(正しいもの)でなければ意味がない」という洗脳にかかった結果、自身の思うままの研究ができなくなる「研究恐怖症」にかかる、というツイートを引用しておられました。つまり、“とらわれてしまう”ということだ思いますが、対策はありますか?
教育の進め方としてそこは本当に難しいと思っています。僕自身は科学の面白さも美術のワクワクする部分も一緒だと思いながら、それを自分の根っことしてやってきました。でも、そう思えない人もいますよね。そういう人たちがどういうスタンスを取るかについては、やはり自分なりのものを見つけてもらうしかない。
言いたいのは、わからないまま自分を閉じ込めないでね、ということ。例えば、デザイナーの場合、何か工学的な問題に直面したときに、数学が苦手でも「工学を使えばこんな問題がこんなふうに解けるらしい」とわかったら、一応自分で勉強してみる。逆に工学系の人なら、「なんかこの書類って自分がつくったものよりかっこいいな」と思ったら、自分なりに解析して、わからなければデザイナーに聞いてみる。せめてそんなふうに行動してほしいし、それが大事。わからないなと思ったときにほうっておかないこと。自分を閉じ込めることなく、さまざまなことに触れながら、自らのコアを見つけていってほしいのです。(取材・文・写真/東京都立大学 インダストリアルアート学域 一色 壌、出井靖伸、イルストレジゼル、大房海渡、富田桃香、野澤桃華、船木梨里花)

山中俊治/1982年東京大学工学部産業機械工学科卒業後、日産自動車デザインセンター勤務。1987年よりフリーのデザイナーとして独立。1991年より94年まで東京大学助教授を務める。1994年にリーディング・エッジ・デザインを設立。2008〜12年慶應義塾大学 政策・メディア研究科教授。2013年4月より東京大学教授。2023年より東京大学特別教授。デザイナーとして腕時計から鉄道車両まで幅広い工業製品をデザインする一方、技術者としてロボティクスや通信技術に関わる。大学では義足や感覚に訴えるロボットなど、人とものの新しい関係を研究している。2004年毎日デザイン賞受賞。ドイツiF Design Awardやグッドデザイン賞など受賞多数。2010年「tagtype Garage Kit」がニューヨーク近代美術館パーマネントコレクションに選定。著書に「デザインの骨格」(日経BP社、2011年)、「カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢」(白水社、2012年)など。
2024年3月29日(金)から21_21 DESIGN SIGHTにて、山中俊治さんが展覧会ディレクターを務める「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」が開催されます。