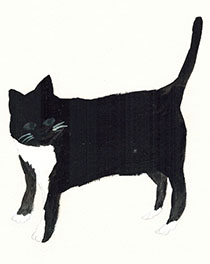熊本県の「つなぎ温泉ホテル 四季彩」のエントランスに設置されたテキスタイルアート(2025)。Photo by Kentaro Ito
日本の若手テキスタイルデザイナーたちは近年、従来の枠組みにとらわれず独自の手法を追求し、その表現は多彩に広がっている。そのなかで庄司はるかは、建築空間のテキスタイルを活動の軸に据え、感性豊かな表現が魅力である。2018年に自身の事務所Haruka Shoji Textile Atelierを設立以降、図書館やホテル、オフィスなど、多様な空間のテキスタイルを手がけている。この9月には、平安伸銅工業から自身初の工業製品となる「One Fit Cloth」を発表した。注目を集める庄司に、デザインに対する考えを聞いた。


愛媛県西予市役所のオフィス改革の一貫としてファブリックを設置(2022)。視線は抜けるが目線は合わない、軽やかな場づくりを目指した。設計は、オープン・エー。Photo by Tomoyuki Kusunose
ロンドンの大学でテキスタイルデザインを学ぶ
庄司は1990年に生まれ、父親の転勤により各地を移り住む幼少期を過ごした。高校時代、まだ将来の目標は明確ではなかったものの、「暮らしに関わる仕事がしたい」という漠然とした思いを抱いていた。そんななか、美大を目指す友人からデザインという分野があると聞いて興味を惹かれた。
ロンドン芸術大学に入学し、1年の基礎課程を終えたあと、テキスタイルの織り専攻を選んだ。「織りのスタジオを見学した際に、機械式だけでなく、アナログな手織り機もあって、色彩豊かな染料や糸が並んでいる光景を目にして、とても魅力を感じました。卒業後のことを考えれば、就職につながりやすい技術を学べる専攻を選んだほうがよいのではないかと少し迷いましたが、最終的にやはり心を惹かれた織り専攻を選択しました」と当時の思いを語る。

石垣島のホテル「MEGURU | 巡」(2022)。1F共用部を仕切るオーガンジーのカーテン。Photo by Miyashita Natsuko

石垣島のホテル「MEGURU | 巡」の客室のカーテン。Photo by Miyashita Natsuko(写真左)
石上純也の事務所で大きな転機を迎える
2014年にロンドンの大学を卒業して帰国。就職活動中に、建築家の石上純也の事務所junya.ishigami+associatesの求人広告に目がとまり、応募を決めた。主に書籍や雑誌の編集をサポートする仕事だったが、そこでの経験が大きな転機となった。
「石上さんの広い視野から考えて核心に迫る設計の姿勢に、とても驚きました。これまでの私は、テキスタイルをデザインするときに、テキスタイルだけに向き合って考えていましたが、ここでの経験を通じて、空間全体との関係性のなかで最適なものを考えるという視点が自分のなかに芽生えたことを実感しました」と庄司は語る。

広島のオフィスのソファの張り地をデザイン(2021)。ニードルパンチ加工のデニム生地を採用し、コミュニケーションが創出されやすいように明るくポップなデザインの柄を考えた。建築設計は、植原雄一建築設計事務所。Photo by yurika kono
さらに、事務所のスタッフから建築空間のテキスタイルワークを手がける国内外のデザイナーやプロジェクトに関する話を聞くうちに、自身が幼少期に興味を抱いたことを思い出したという。
「家族旅行で訪れた香川県の直島で、自然環境や建築空間とアート作品が融合したインスタレーションに強く惹かれた記憶が蘇りました。建築の中のアート作品のように、建築の中のテキスタイルも社会的な役割や新たな環境を生み出すことができると知ってより関心が高まり、自分もそういう仕事に携わりたいと思いました」と語る。石上の事務所に1年勤めたあと、退職を決めた。

東京・渋谷区のオフィスのテキスタイル(2025)。建物の開口部に使用されている波板のような陰影を生地にプリントした。空間設計は、植原雄一建築設計事務所。Photo by So Mitsuya
空間のテキスタイルを軸に活動をスタート
KAJIHARA DESIGN STUDIOに2年ほど勤務したのち、 2018年に独立してHaruka Shoji Textile Atelierを設立。最初は、いくつかの建築事務所に間借りして仕事をしていた。ちょうどその頃、石上純也の事務所で働いていたときに知り合った若手建築家らが独立し始め、彼らが設計する建築空間のテキスタイルの依頼を受けるようになる。完成したプロジェクトが掲載された媒体を見た人や、人のつながりを通じて徐々に仕事の幅が広がっていった。

静岡県立美術館の「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」展のためのテキスタイル(2025)。展示されている絵画作品から色彩や光の陰影を抽出し、パッチワークの技法でつなげてテキスタイルに表現した。展示空間デザインは、建築家の桂川大(STUDIO大)、おどり場。Photo by ToLoLo studio Mayu Nakamura
近年、手がけた仕事のひとつに、2024年12月に開館した高知県の「佐川町立図書館さくと」がある。
佐川町は植物学者の牧野富太郎の出身地であり、四季を通じて多種多様な植物が見られる地域として知られる。庄司はまず、この街のことを知ることが大事だと考えてリサーチに訪れ、プロジェクトのチームメンバーと散策して周った。その際に佐川町で草木染めをしている作家を紹介され、作家が地元の植物で糸を染め、それを見本帳としてまとめていたものを見せてもらう機会を得た。庄司は、その色合いや街で見た風景をもとに、カーテンのデザインを決めた。
「建物は多角形をしていて、館内を周遊できるように設計されています。そこでエリアごとにカーテンの色を変え、来館者が館内を巡りながら、居場所の変化を楽しめるように工夫しました」(庄司)。

高知県の「佐川町立図書館さくと」のカーテン(2024)。プリント技術によって、ポリエステル素材でも草木染めのような豊かな色彩を表現できることを提案。建築設計は、ハウジング、森下大右、イシバシナガラ設計共同企業体。Photos by Yikin Hyo
最新のプロジェクトは、熊本県の葦北郡津奈木町の温泉施設を改修した「つなぎ温泉ホテル 四季彩」だ。今回も庄司は、この土地を深く知ったうえで制作したいと思い、津奈木町に2週間ほど滞在。まちから借りた電動自転車で朝昼晩と周辺をかけ巡り、そこで感じたことをテキスタイルに表現した。山の斜面に広がる柑橘畑や津奈木町の海の静けさと美しさを思わせるような、情感豊かなデザインが印象的だ。

左は、熊本県の葦北郡津奈木町の風景。朝焼けの時間の海の色は、なんとも豊かだ。右は、庄司がトレーシングペーパーで制作したテキスタイルアートの模型。

熊本県の「つなぎ温泉ホテル 四季彩」のテキスタイルアート(2025)。窓からの光を内部空間に届けるために、布の長さを変えてデザインの工夫を凝らした。リノベーション設計は、オープン・エー。Photo by Kentaro Ito
環境との関わりを大切に考える
庄司は、ほかのテキスタイルデザイナーのようなオリジナルブランドをもたず、空間のテキスタイルを手がけることに注力している。その理由をこう語る。
「私は自分のブランドを展開することにあまり関心はありません。私にとって布とは、職人さんにとっての工具のような道具であり、最も興味があるのは、それを使って居場所や環境をつくることです。この場所をどんな空間にしたいか、ここを訪れる人にどんな時間を過ごしてもらいたいか、そして、これからどんな場に育ってほしいかということを常に大切に考えています。私は布という道具を使って、周囲の環境を含めたその場に生まれる人の体験をデザインしたいのです」。

ダンサーasamicro(@egglife_asamicro)が2022年に上演した「Drowning in Breakfast」の舞台美術を制作(神楽坂セッションハウス)。Photo by Kai Maetani

2025年9月に横須賀で開催された展覧会「たにそこを叩く」内でasamicroが行ったパフォーマンス。2022年に制作した布を新たな見せ方で使用した(Yokosuka art valley HIRAKU)。Photo by Kai Maetani
この9月には、平安伸銅工業から自身初の製品となる「One Fit Cloth」を東京ビッグサイトで開催されたLIFE×DESIGNの展示エリア「FOCAL POINT」で発表。最初にどういうものをつくるかということを、平安伸銅工業と対話を重ねたという。そして、第一弾として透け感やカラーの異なる素材を上下、あるいは左右で切り替えた「つなぐ」シリーズを開発。一般的なカーテンより幅は細いが、両端のボタンでつなぎ合わせることで大きな面をつくることができ、折ってクリップでとめれば、好きな長さに調節できる。これまで庄司が手がけてきたホテルやオフィスのような大きな建築空間と同様に、日常生活のなかの小さな空間を彩るテキスタイルである。

「One Fit Cloth」平安伸銅工業(2025)。第一弾の「つなぐ」シリーズでは透け感のある素材から、メタリックな光沢をもつものまで全13種類揃う。シワになりにくい素材で、自宅での洗濯が可能。断熱性やUVカット機能(UV99%カット)をもつ素材を組み合わせたものもある。

「One Fit Cloth」平安伸銅工業(2025)。ボタンをとめて連結することで、パッチワークのようなパターンが生まれる。
今後携わってみたい分野は、ひとつは幼少期に転勤が多かったことから興味を惹かれるという、乗り物や空港、駅などに関わるテキスタイル。もうひとつは、ホスピタルアートのように、素材や色彩を通じて癒しや安らぎ、元気を与えるような病院やクリニックのテキスタイルに取り組んでみたいと願望をのぞかせる。近年では富山県高岡市の小児科のカーテンを制作したり、この秋には保育園の子どもたちと布を使ったワークショップを開催する予定だ。
庄司はこれからもテキスタイルデザインの可能性を押し広げながら、多様な環境に豊かさと彩りを添え、新たな価値を創出することを目指していきたいという。![]()

庄司はるか/テキスタイルデザイナー。1990年生まれ。イギリスの美術大学を卒業後、建築設計事務所、テキスタイルデザイン事務所勤務を経て、2018年Shoji Textile Atelierとして独立。建築空間向けのカーテンやソファ生地のデザイン制作を中心に、テキスタイルを用いた作品も制作している。