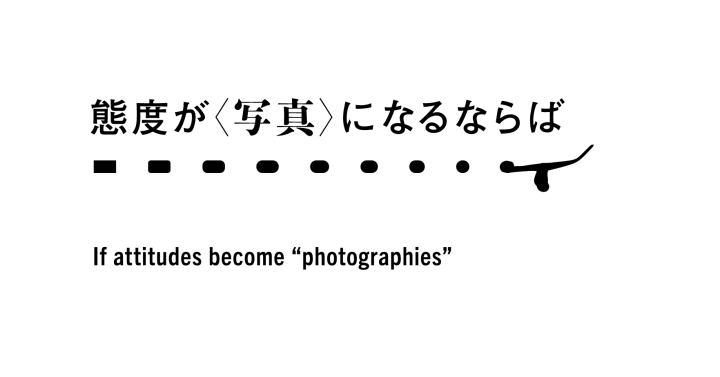INTERVIEW | アート / カルチャー / 展覧会
2025.10.24 18:31

東京の都市空間を“ギャラリー”に見立てた、東京から世界へ向けて発信する写真芸術の祭典「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」。7回目の開催となる今年は、「Garden」というテーマのもと、八重洲・日本橋・京橋・銀座を中心とした日本を代表する街並を舞台に、都市の隙間や余白を「庭=創造の場」へと変貌させる作品展示が行われている。
その中核プログラムのひとつ「City as Garden」では、写真家スティーブン・ショア(Stephen Shore)、スティーブン・ギル(Stephen Gill)、そしてメリッサ・シュリーク(Melissa Schriek)の3名を迎え、彼・彼女らの作品が東京という都市を彩る。
今回AXIS webでは、T3に合わせて来日したメリッサ・シュリークとスティーブン・ギルに特別に話を伺う時間をいただいた。本稿ではスティーブン・ギルのインタビューをお届けする。
長年にわたり「土地」や「自然」と向き合いながら、自身の介入を極限まで抑え、被写体自身が語りかけるような作品を追求してきたスティーブン・ギル。キャリアを代表する「Hackney」シリーズの制作背景から、当作がその後の『Talking to Ants』、『Night Procession』や『The Pillar』に、いかに影響を与え、意図とチャンスの融合で各作品を生み出したかなど、偶発性を重んじる独自の撮影手法の、奥深い創作哲学を伺った。
――T3へのオファーを受けたときの心境をお聞かせください。
スティーブン 日本が大好きなので、このオファーをとても嬉しく思いました。加えて「City as Garden」というテーマにも惹かれました。私は長年「自然」を主題に扱ってきたので、とても共感できるテーマだったんです。
――今回、『Hackney Flowers』という作品を、「泥染め」した和紙にプリントした貴重な展示を行っています。このコラボレーションについても伺っていいですか。
スティーブン 基本的に私は自分の作品に対して、自分自身が深くコミットし、紙質や色味など、細部にまでこだわりを持って制作をしています。でも、年を重ねるにつれて、少し力を抜くことも学んでいるんです。人生のすべてを完璧にコントロールしようとして、すべての細部にまでしがみつくことはできない、ということも理解するようになりました。だからこそ、自らの作品を他者に委ねる今回のコラボレーションの誘いを受けたときは嬉しかったです。奄美大島の職人の方の手によって生まれ変わった私の作品のクオリティは、私が求める精密さを宿していました。プリントを見たときはとても感動しましたね。

奄美大島の染色家・金井志人さんによる泥染めを施した和紙にプリントされた写真5点を展示している。ハックニー・ウィックと奄美大島、ふたつの土地の記憶が混ざり合った新たな表現に注目してほしい。
――『Hackney Flowers』は、ロンドンのハックニー・ウィックというエリアの風景やひとびとを撮影したキャリア初期の代表的作品『Hackney Wick』の続編とも言える作品ですよね。そもそも『Hackney Flowers』をつくろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
スティーブン 『Hackney Wick』は、撮影するにあたって「ハックニー・ウィックという場所であること」以外に特にルールは設けていませんでした。ただ制作中は、自分が歩んだことのない道に踏み込んだような感覚に陥りました。そのときは、自分が作品をつくっているという感覚はなく、むしろ作品の方が自分をつくっているように感じたんです。何かが朝5時や6時に自分を起こしてくれているような、そんな感じで。
そして、『Hackney Wick』をつくり終えた後、「この場所にはまだ何かがある」という考えが頭をよぎりました。いつも同じ例えを使うのですが、濡れたタオルを絞るように、もっとハックニー・ウィックから抽出したいという気持ちが湧いてきたんです。そして出来上がったのが『Hackney Flowers』でした。だから私はこの作品を、一種の「抽出」として捉えています。物を拾い上げたり、配置し直したりしながら、その場所から被写体を抽出し、それがその土地の“時間”そのものではなく、“その土地の性質や精神、またそれらが私に引き起こす感情”を写し出すことを願っていたんです。

『Hackney Flowers』:当時スティーブンさんが住んでいたハックニー・ウィック地区で採集してきた花や種、実、葉などを、自身のスタジオで乾かし、潰し、同地区で撮った写真の上に配置しながら撮影している。© Stephen Gill / Hackney Flowers 2004–2007 / Courtesy of Christophe Guye Galerie
――そうした動機から、なぜタイトルにも用いられた花をはじめとする植物を作品のモチーフに選んだのでしょうか。
スティーブン ハックニー・ウィックは工業エリアで、非常に混沌として、矛盾に満ちた街でした。あらゆるものが吐き出され、集まってくるような場所だったんです。そして、そこにはあらゆる種類のひとびとや場所が隣り合わせに存在していました。公園、バスステーション、市場、教会、工事現場——そんなものがすぐ隣り合わせにあって、あらゆる方向に引っ張られているような場所でした。
そんな多様な個性がごちゃまぜになった街で、どの場所にも存在しているのが植物だったんです。それが花や種、葉に惹かれた大きな理由でした。
――『Hackney Flowers』では、ハックニー地区で集めた植物をはじめ、さまざまな自然物を撮影した写真の上に散りばめ、さらに再撮影するという手法を用いています。そうしたプロセスはデザインやアートワークに近いのでは、と感じています。
スティーブン 『Hackney Flowers』は、写真を撮るのではなく、“つくる(build)”感覚でつくった初めてのシリーズです。普通、写真を撮るとなると、被写体に対してカメラや自分の位置を調整しますよね。でもこの時は初めて完全に固定したカメラで撮影したんです。3年間、毎週末に医療用カメラをレンタルし、エリアを散策する中で拾った花、種などの被写体を相対的に動かしながらカメラはフィックスで撮影しました。構図は似通ったものになってしまいますが、フレームの中で、自身の調和や不調和の感覚に基づいて、被写体を動かしていくことで、顕になる部分と隠れる部分が混在してとても面白い体験でした。
しかし、この『Hackney Flowers』 の制作後、もっと自分の作為を減らしたいと思いました。写真を“つくる”痕跡が残りすぎていたんです。その結果、次に取り組んだのが『Taking to Ants』という作品でした。この作品では被写体となるオブジェクトをカメラの内部に入れて、撮影中にカメラを揺らしました。オブジェクトはフィルムの上で動きながら、シャッターの開閉の瞬間に偶然の像を残す。つまり、完全にランダムなプロセスによって生まれた作品だったんです。
制作のプロセスにおいて、「デザイン」という感覚は自分にはありませんね。主題である被写体こそがすべてで、最近では美学さえもあまり重要だと思っていません。もちろん、本を制作するときには、ある程度のフレームワークを意識する必要はありますが。
※『Taking to Ants』:イースト・ロンドンで収集した物をカメラのボディに入れて撮影した作品。カメラの中で物が衝突したり、調和したりしながら、最終的なイメージはスティーブン自身も予想がつかないものに仕上がる。

――できるだけ撮影者である自身の介入を抑え、新しい写真表現を探求するモチベーションはどこから生まれてくるのでしょうか?
スティーブン やはり私は、被写体自身に語らせたいのだと思います。
私はその後、ロンドンからスウェーデンに移り住んだのですが、当時はスウェーデンのことをあまり知りませんでした。だから、スウェーデンの自然の景色を目にした時、「これが本当の自然の世界だ」と決めつけるようなことはしたくなかったのです。むしろ、そこにある自然、被写体に主導権を持たせ、作品をつくりたいと考えました。つまり、自分が主導するのではなく、被写体に導かれるという感覚ですね。その後の作品は、その流れに従うようにしたんです。『The Pillar』では鳥、『Night Procession』はスウェーデンの自然に生きるあらゆる動物たちが作品をつくってくれています。自分はオーケストラの指揮者のような意識でいます。
そしていちばんワクワクするのは、ついに自分という存在が写真から離れたと感じられる瞬間です。「これは良い写真だ」「これは完璧な瞬間だ」と、人間が判断することがなくなった感覚と言えばいいでしょうか。 そうした写真は、すべてが“ズレた瞬間”の積み重ねでできているような感じがします。そうすることで、被写体により近づける気がするんです。 特に『The Pillar』では、まるで“病室の扉”を開けて、半分はこの世界に、もう半分は別の世界に足を踏み入れたような感覚がありました。
※『Night Procession』:2014年、長らく暮らしたロンドンを離れ、パートナーの故郷であるスウェーデンに移住したスティーブン。荒涼とした自然の風景は、昼と夜で異なる景色を見せることに気づき、近所の森に設置した赤外線感知式のカメラで、野生の鹿やフクロウなどの動物や自然の姿を捉えた作品。
※『The Pillar』:家の近くに鳥が休むことのできる木製の杭を立て、その杭の前に動体感知式カメラを設置し、野鳥の姿を4年にわたって定点記録した作品。知られざる野鳥の姿が見事に写し出されている。
ーー『The Pillar』や『Night Procession』がまさにそうですが、カメラを手に持たず、自分でシャッターを押さないこともありますよね。決定的瞬間に自分でシャッターを押すことが、カメラマンの誇りだとも思っていたのですが、カメラマンの身体性についてはどうお考えですか。
スティーブン これは難しい質問ですね。しかしとても不思議なのですが、たとえカメラを手にしていなくても、常に「見る」こと、「目を鍛える」ことはできると思っています。ロンドンにいた頃は、目を凝らしてボタンのような小さな“宝物”を探すことをある種の訓練のように続けていました。今でも、撮影が難しい蝶を撮ることで、自らの視覚を鍛える「バタフライトレーニング」を続けています。
話が外れましたが、しばしば写真家は、ある種の先入観や目的にあまりにもフォーカスしすぎて、結果的に見えているものが少なくなってしまうことがあります。写真というものは、「これは〇〇についての作品です」と決めつけすぎる危うさもあると思うんです。「これはインドのこのコミュニティについての作品だ」と言っても、実際のところ、それが真実を語っているとは限らない。だから、私たちが写真を通じて主張し、語り、見せようとするものは、必ずしも深い真実ではないと思います。
自分の話に戻すと、『Night Procession』を制作していた数カ月間は、五感が極端に研ぎ澄まされていました。まるでラジオの周波数を調整するように、森の波長にぴたりと合わせると、予感のようなものが感じられたのです。「1時間後に枝の上に鳥がとまるから、そこにカメラを構えよう」と思いつき、夜のうちにカメラをセットして翌朝戻ってくると、そこに鳥がいたんです! 言葉にできない、決定的瞬間を越えた体験でした。質問の答えになっているかわかりませんが、パターンや癖の理解を深めることができるあのような体験が私は本当に好きなんです。
――興味深い話をありがとうございます。最後に読者に向けてメッセージをいただけますか。
スティーブン 自分がデザイン誌を読んでいるような方たちに語れることは多くないと思いますが、もしあなたが何かをつくる、あるいは何かに取り組むのであれば、その対象、つまり被写体やモノの声に耳を傾けることが大事だと思います。 そして、自分自身のエゴ、あるいは自分のMacBookのようなツールで、それを窒息させてしまわないこと。そういう姿勢がとても大切なんだと思います。(文/AXIS 平木輝正)![]()

スティーブン・ギル/1971年、イギリス・ブリストル出身。ファウンドオブジェ、身の回りのエフェメラ、周辺環境による作品への介入を制作過程に組み込みながら、写真を中心に幅広く活動するアーティスト。場所と自身の体験を基盤とし、観察的かつ直感的なアプローチで数々の作品を生み出してきた。スウェーデンの地方に移住して以来、自然、記憶、そして写真の物質性の関係性を探求するようになった。プリントを土に埋めたり、ネガにさまざまなモノを重ねたり、自然の力でイメージが加工されるよう促したりなど、型破りな技法をよく用いる。
T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO
- 会期
- 2025年10月4日(土)〜27日(月)
- 会場・時間
- スティーブン・ショア|東京ミッドタウン八重洲(11:00-21:00)
スティーブン・ギル|東京建物日本橋ビル(平日 7:00-20:00、土祝 8:00-17:00)
メリッサ・シュリーク|東京建物八重洲ビル(平日 7:00-20:00)|三栄ビル(終日) - 入場
- 無料
- 詳細
- https://t3photo.tokyo/