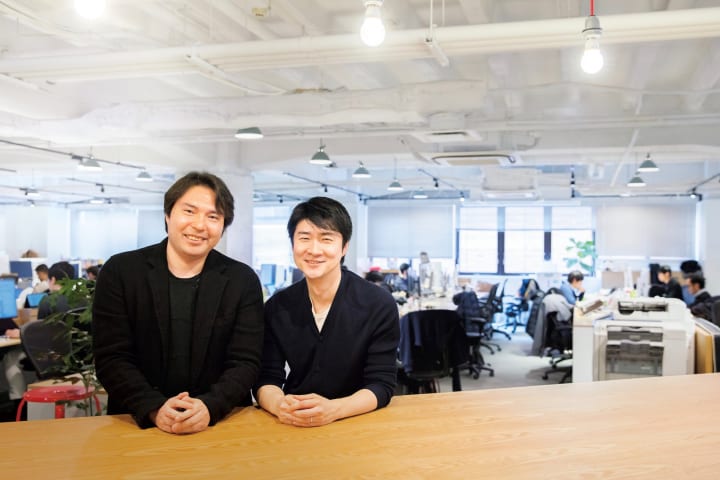
デザイン・イノベーションファームTakramの田川欣哉がナビゲーターとなり、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブの3領域をつなぐトップランナーを迎える連載「BTCトークジャム」。今回のゲストは、スマートニュース代表取締役会長・共同CEO(※1)の鈴木 健さんです。
※1 2018年2月取材当時。現在は、代表取締役会長兼社長 CEO(最高経営責任者)。
トーク音源はこちら
最高のユーザー体験を
田川 すごく開放的で気持ちいいオフィスですね。ここで何人くらいが働いているんですか?
鈴木 アルバイトなども入れて、百数十人です。あとはニューヨークとサンフランシスコに20人くらいいて、3拠点でやっています。世の中にはいいコンテンツをつくっている人たちやパブリッシャーがたくさんいる。そこからコンテンツをお借りして配信しているのが「スマートニュース」というアプリで、そのシステムをつくるため、スタッフの約半分がエンジニアですね。
田川 同じエンジニアでも、機械学習系のアルゴリズムまわりのエンジニアとアプリのフロントエンドをつくっているエンジニアでは役割が違うと思いますが、そこはきっちり決まっているんですか?
鈴木 決まっていますね。最初は共同創業者の浜本(階生)がサーバーサイドもアプリサイドもひとりでつくっていたんですが、メンバーが増えていくにつれて、どんどんチームが分かれていきました。
田川 すでに国民的アプリとなっているスマートニュースを知らない人はいないと思いますが、読者にあらためて紹介いただけますか。
鈴木 5年ほど前にスタートしたニュースアプリで、今は日本と米国をメインに展開しています。グローバルで2,500万ダウンロードくらいです。コンセプトは「ディスカバリー」。ユーザーにとって発見があるような情報を選んで配信していくことを大事にしています。その情報を人間の編集者ではなく、アルゴリズムが選んでいるのがポイントです。機械学習を使ってその人にとって読むべきコンテンツ、発見になるであろうコンテンツを配信しています。

▲ニュースアプリ「スマートニュース」のコンテンツ表示例。電車内の中吊り広告にヒントを得た「違い棚方式」と呼ばれる情報レイアウトを採用している。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
田川 スマートニュースのベータ版みたいなものが世の中に出てきたときのことを今でも覚えています。情報をローカルにキャッシュしておき、待ち時間なしで地下鉄の車内でも読める。当時のモバイルネットワーク環境の課題をテクノロジーで解決する一方、横フリックでタブを切り替えるアイデアも実装していました。この縦スクロールと横のフリックの方式がiPhoneのアプリで純正のアルゴリズムではなかったことに驚いて、当時それを鈴木君に話したんですよね。
鈴木 そこに気づいたのはさすがだと思いました。浜本がUXデザイナーの川原英哉さん(元Takram)と組んで目指した最高のユーザー体験は、当時のアップルやグーグルの標準APIを使っても実現できなかったんですね。今はスマホのスペックが上がっているので、われわれが“ヌルヌル感”と呼んでいるスワイプのなめらかさを出せるのですが、当時は自前でアニメーションを描いていくしかなかった。職人的な力、こだわりの力でつくり出せたのだと思います。ふたりで何週間もかけて、あらゆるパターンを試しました。ディテールの細かさも他のアプリとは違ったので、ある種の衝撃をユーザーに与えたと思うんです。
田川 ローカルにニュースコンテンツがキャッシュされて待ち時間がないのは、どちらかというと仕様的な工夫ですね。そこに体験レベルの引っかかりのなさがマッチしたんだろうなと思います。
鈴木 コンポーネントに分けると、まさにそのふたつです。ユーザー体験で最も支持されるのは“サクサク”としたスムースな動作。当時のスマホでニュースをブラウザで読んでいると、ページをめくるのにも突っかかるし、タップしてコンテンツを読もうとしても待ち時間が発生する。とにかく突っかかる体験がすごく多くてストレスフルでした。それを技術とこだわりの力で乗り越えたんです。
オフラインの話だと、当時は地下鉄が圏外でした。あるとき電車に乗っていて隣を見たら、スマホでゲームをやっているわけです。反対側を見てもゲームをやっている。そういう自分もやっぱりゲーム(笑)。通信回線がないから、みんなゲームしかやることがなかった。
田川 それに気づいたタイミングと、スマートニュースをつくろうと思ったタイミングは、どちらが先でしたか?
鈴木 スマートニュースに至るプロジェクト(PCブラウザに向けたニュースキュレーションサービス「Crowsnest」)がすでにあったんですが、その半ばでスマホアプリの必要性に気づきました。本当にそれがキラーコンテンツになるのかまでは確信がなかったけれど、議論していくなかで「やったほうがいいね」という話になったんです。

▲鈴木 健(すずき・けん)/1975年長野県生まれ。98年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。伝播投資貨幣「PICSY」が情報処理推進機構の未踏ソフトウェア創造事業に採択、天才プログラマーに認定される。12年にスマホ用ニュースアプリを開発・提供するゴクロ(現スマートニュース)を設立。著書に「なめらかな社会とその敵」がある。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
在野のクリエイターの感度
田川 BTC的な話で面白いと思ったことがあります。「ネットワーク環境がないから地下鉄のなかでみんながゲームをしている」といった観察は、デザイン的にはインサイトと呼ばれる気づきのレベルなんですが、その話とテクノロジー視点の解決が掛け合わされてプロダクトが生まれていった点です。
鈴木 当時はビジネスのことを全然考えていなくて、どちらかと言うとクリエイティブやテクノロジーで飛び抜けたもの、突き抜けたものをつくりたいという気持ちがありました。英哉さんが最初にモックをつくってアドバイスしてくれたこともあり、デザイン的に目を引くものができたのだと思います。
田川 デザインチームは、社内ではどんな感じになっているんですか。
鈴木 プロダクトのデザインをしているスタッフが2名います。彼らは正規のデザインやエンジニアリングの教育は受けていなくて、ものをつくるために独力でエンジニアリングもデザインも勉強してきた、ある種「在野のクリエイター」というタイプです。
田川 必要なら何でもやるというタイプですね。ナチュラルボーン・ハイブリッドだ。カーデザインやインダストリアルデザインだと歴史が長いから教育側に体制があるんだけど、アプリやUIといった情報系のデザインは教育が追いついていない。だから在野のほうがスキルの習得が全然速いのでしょう。
鈴木 ユーザー体験やデバイスがアップデートされるスピードが速いから、教育が追いつかない。彼らのほうがキャッチアップが速くて、新しい体験がつくり出せるんですね。それに加えて、アプリ開発企業の「ディヴィデュアル」がスマートニュースに参画することになったので、彼らが新しい風を送り込んでくれると期待しています。
田川 ディヴィデュアル買収のニュースがちょうど発表されましたね。共同創業者のドミニク(チェン)さんなど、ブレインパワーの大きな人たちがガチャッと入った印象です。ここまではデザインチームの話でしたが、ビジネスチームとテクノロジーチームはどんなコラボレーションをしていますか?
鈴木 基本的にはプロジェクト単位で動きます。例えば1個のプロジェクトが立ちあがったらまずリーダーを立てるのですが、そこにビジネスサイドから3名、エンジニアリングから6名関わるといった具合です。そうしたコラボレーションは横断的に日々行われています。
チーム間の垣根はつくりたくないから、オフィスデザインは重要です。そのためワークスペースは分けていません。エンジニアの人もビジネスサイドの人も同じフロアにいるので、すれ違って話をしたりとか、コーヒーを飲むときにたまたま列で一緒になったときにコミュニケーションを取ったりしています。イベントスペースで毎日ランチを出しているのですが、あえて相席になるよう長い机を並べています。こうした設計はグーグルの手法を採り入れたものです。


▲国内外・多ジャンルからなる情報誌が集められた「NEWS STAND」や、靴を脱いであがるフリースペースなど、社員同士が気軽にコミュニケーションをとれるオフィス環境になっている。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
情報への距離を再設計する
田川 鈴木君は「なめらかな社会とその敵」という本を書いて話題になりましたね。これはいつ出版されたんでしたっけ。
鈴木 スマートニュースをリリースした1カ月後なので、ちょうど5年前です。あの頃は本当に忙しかった。
田川 今日の話のなかでも「なめらかさ」というキーワードが何回か出てきました。本の中には「なめらかな社会」というユートピア的な理想像があって、そこに至る方法論が記されているんですが、それとスマートニュースでやっていることが鈴木君の中でどうつながっているのかな。理論と実装という話になったときに何かあるんじゃないかなと思うんだけど、どうですか?

▲鈴木氏の著書「なめらかな社会とその敵」。「この複雑な世界を、複雑なまま生きることはできないのだろうか」という一節から始まり、ものごとを単純な二元論に還元せず、複雑なものを複雑なまま理解する「なめらかな社会」の構築を目指す。実践的な手段として「伝播投資貨幣PICSY」や「分人民主主義Divicracy」といったシステムを数理モデルとともに提唱した。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
鈴木 貨幣や投票、軍事といったシステム、社会契約論などいろんなことが書いてあるんですが、「情報の距離」の再設計ができないかとも思っていました。情報には自分の近くにある情報と、地球の反対側にあるような遠い情報の両方があるじゃないですか。人というのは、自分に近い情報にも、地球の反対側の情報にも興味がある。それらをいかにバランスよく得られるようにするかを昔から考えていて。最初にグーグル検索を見たときに「これって情報の距離をデザインしているんだ」と思ったんです。
検索枠の1ページ目に出てくると皆クリックするけれど、100ページ目なんて誰も見ないわけです。ひとつのキーワードを入れたとき、情報への距離がグーグルのつくったアルゴリズムによってデザインされている。本当は人によって違っていてもいいのだから、その距離は本当に正しいのかと疑問に思ったわけです。
田川 そうした問題解決の実装として機械学習がリコメンドするニュース配信のアプリを選んだことが面白いなと思います。スマートニュースでやっているのはニュースを通じてディスカバリーを届けることだという話が最初にありました。この仕事の先にやりたいことも頭の中にいっぱいあるんじゃないかと想像するのですが、どうですか?
鈴木 まだ妄想しかないですけどね。いくら地球の反対側にある情報にアクセスできる時代になったと言っても、実は、言語や国境を越えてまで情報は流通していません。僕たちもかなり日本語のコンテンツに依存してるし、英語のコンテンツを読んでいたとしても、すごく偏ってるわけです。僕はアラビア語のコンテンツは読めないですからね。人々は全然違う視点で生きている。地球の反対側で起きているニュースもきちんと読めるような状況をつくらないといけないなとは思っています。
言語と国境を超えて情報を流通させるのも大事なんですが、一方で最終的に情報を得るときにどういう態度で受容するのかということがより大事になってくると考えています。


▲鈴木氏が瞑想室と呼んでいる、数学者アラン・チューリングの足跡、暗号解読や計算機の歴史をテーマにした本棚があるオフィス内の部屋。デザインは小石祐介氏によるもの。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
田川 ニュースというのは、情報を摂取するためのインフラですよね。次の段階には貨幣システムがあったり、民主主義のシステムなどもある。鈴木君の関心の向かう先は、社会の土台になっているレイヤーにあるのかなと今日の話を聞いていて思いました。
鈴木 僕たちが日々生きているなかで、社会に「違和感」を感じることがありますよね。大人になるとあまり感じなくなるかもしれないけれど、子どもの頃にはよく感じていたと思うんです。その違和感にはちゃんと理由があり、原因を探ると、どんどん本質的な深いところに向かっていく。ちゃんと掘っていった結果として、違和感の源がそこにあるんだと気づくんです。そこまでいかずに解決しても、表面的なものに止まってしまうという危惧はあります。
田川 原因の本質のようなものが処理されないかぎり、表面をいくら理解したつもりになっても、また違う違和感が湧いてくる。だからこそ、その根源的なところにアプローチしたい、ということなんですね。原因のひとつには個人と情報との誤った距離設計があるから、それを解決するためにスマートニュースをやっていますということなんですね。
鈴木 そうです。あまり人に伝わらないんですけどね(笑)。![]()

▲田川欣哉(たがわ・きんや)/1976年生まれ。Takram代表。東京大学機械情報工学科卒業。ハードウェア、ソフトウェアからインタラクティブアートまで、幅広い分野に精通するデザインエンジニア。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート客員教授・名誉フェロー。©井上佐由紀/Sayuki Inoue
ーー「この複雑な世界を、複雑なまま生きることはできないのだろうか」という根源的な問いを、ニュースメディアビジネスをつくりあげることで具体化しようとしている鈴木 健さんは、BTCを地で行くビジョナリーです。物事の構造を深掘りし、その本質を探り当てようとする姿勢や、その本質に対して直接解決を試みるスケールの大きな思考。正真正銘のThought Leader(ソートリーダー)です。(田川)
本記事はデザイン誌「AXIS」193号「工芸未来。」(2018年6月号)からの転載です。
トーク音源はこちら
















