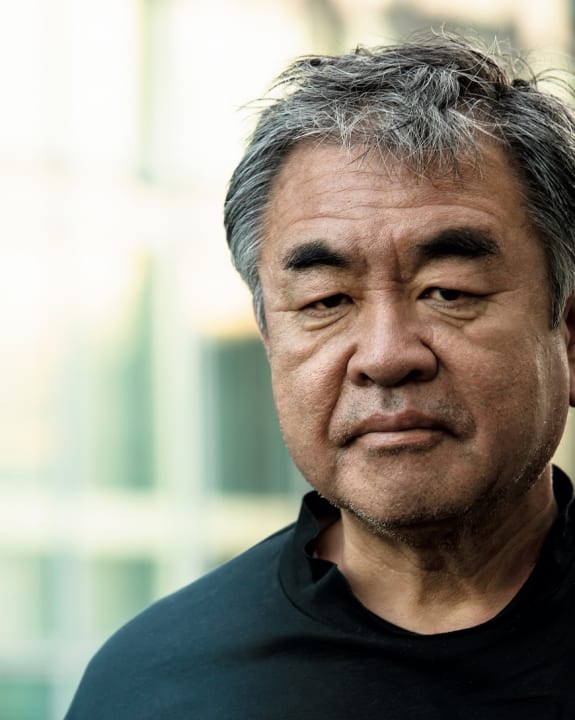INTERVIEW | プロダクト
2019.07.11 07:14

文化は流転する
数年前、東京に住む友人が、新しくオープンした人気のバリレストランへ連れて行ってくれた。インゴ・マウラーの照明が少しと、南国を思わせる装飾品がそこかしこにある店だった。料理はどれも素晴らしかったが、バリ料理というよりは、フレンチと和食を組み合わせた何物でもない料理のように感じられた。さらに困惑したのは、その店の日本人オーナーがバリレストランを始めた理由だ。「今、バリにはフレンチと和食のおいしいレストランがたくさんあるから」と言うのだ。
文化というのは、拡散され、変化し、解釈され、時には誤解されながらもさまざまな土地へと広がっていく。バリにあるフレンチと和食のレストランをモデルにした、東京のバリ料理の店―グローバル・ツーリズムの副産物―は、外国人である私にとって、独自の体系で説明された「日本らしさ」を強く感じさせるものであった。
この出来事は、当時建設中だった博物館M+(香港)につながっている。私たちはM+の建物やコレクションを構築する際に、今改めてアジアを中心にすることによって、世界のデザインに関する物語を捉え直そうと試みていた。アジアという地域のなかで、また他の地域との関わりのなかで、20世紀のデザインを形成した人々のつながりをたどっていったのである。

▲映像文化博物館M+(香港) ©Herzog & de Meuron
バンブーチェア、シェーズロング、そしてバタフライスツール
日本では、柳 宗理を挙げてみる。20世紀のデザイン界において最も偉大な人物のひとりである宗理は、私が学んだ欧米中心のデザイン史には、ほんの脇役程度にしか登場しない。しかし今、彼を中心に据えることで、国境を越えた交流というひじょうに興味深いストーリーが見えてくる。
1920年代から30年代に起こった民藝運動の草分けと言える柳 宗悦の息子である宗理。若かりし頃の彼は、常に父と対立していたという。駆け出しのデザイナーとしての反抗心もあったのだろうが、彼は父親のアイデアを否定し、工業生産を通して表現される、より挑戦的でユニバーサルかつ「モダン」なデザインを好んだのである。
40年、当時25歳だった宗理は、フランス人デザイナーであるシャルロット・ペリアンと出会った。商工省の招待で日本を訪れていたペリアンの任務は、輸出市場に向けた日本の工芸産業への指導である。彼女は宗理を伴って日本中を旅し、41年に髙島屋で開催された「選擇・傳統・創造」展で、その調査の結果を発表した。
ペリアンはその展示会に、三越のデザイナー、城所右文次がその4年前に制作したバンブーチェアを展示した。カンチレバー(片持ち構造)の曲げ木枠を用いたこの椅子は、フィンランド人デザイナー、アルヴァ・アアルトのモデル31チェアによく似ていた。違うところといえば、城所の椅子の座面には、合板の代わりに曲げ加工を施した竹の薄板が使われていた点である。マルセル・ブロイヤーによるスチールパイプの実験からもヒントを得ていたようだ。

▲バンブーチェア 武蔵野美術大学美術館・図書館所蔵
ペリアンは城所の作品に魅了されたのであろう。同じ素材や同じ技法を用いて生み出した作品のなかには、28年にル・コルビュジエやピエール・ジャンヌレと共同でデザインした、スチールパイプを用いたLC4シェーズロングも含まれている。正直なところ、城所とペリアンによる竹材の解釈は、やや不格好なものであるように思える。しかし、宗理の息子・新一が私に語ったように、宗理がペリアンと過ごした時間は、日本の工芸的な感性が工業生産と相容れないものとは限らないという可能性を、宗理のなかに切り拓いてくれたのである。このことがやがて、(日本ではもともと椅子に座る文化がなかったにもかかわらず)日本のデザインにおける最もエレガントな象徴のひとつ、バタフライスツールを生み出すきっかけとなった。

▲シェーズロング(イージーチェア No.LC4) 武蔵野美術大学美術館・図書館所蔵
宗理は、ユニバーサリストとしての姿勢を決して失うことはなかったようだ。「いつか、統合された人類文化から、地域文化たる民藝に備わる純粋性(不純の異物が混ざっていない、美の源泉)が確保されたデザインが生まれるだろう」といったことを宗理は晩年に書いている。それでもなお、宗理の作品の「日本らしさ」について語られる際には、バタフライスツールのシルエットが鳥居と比較されることが多い。
とはいえ、おそらくこれは的外れであろう。「意識的に日本の様式を組み込む必要などまったくない」と、宗理は日本のデザインについて話している。「日本において、日本人の手で、日本社会のために真摯につくられたものである限り、そこで生まれるデザインは必然的に日本的にならざるを得ない。日本の伝統もそういう態度で保たれてきたのではないだろうか?」。まさしくそのとおりである。
これはバリ料理のレストランが、どうしたら日本のレストランになるのかを説明する一助になるかもしれない。![]()
本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。