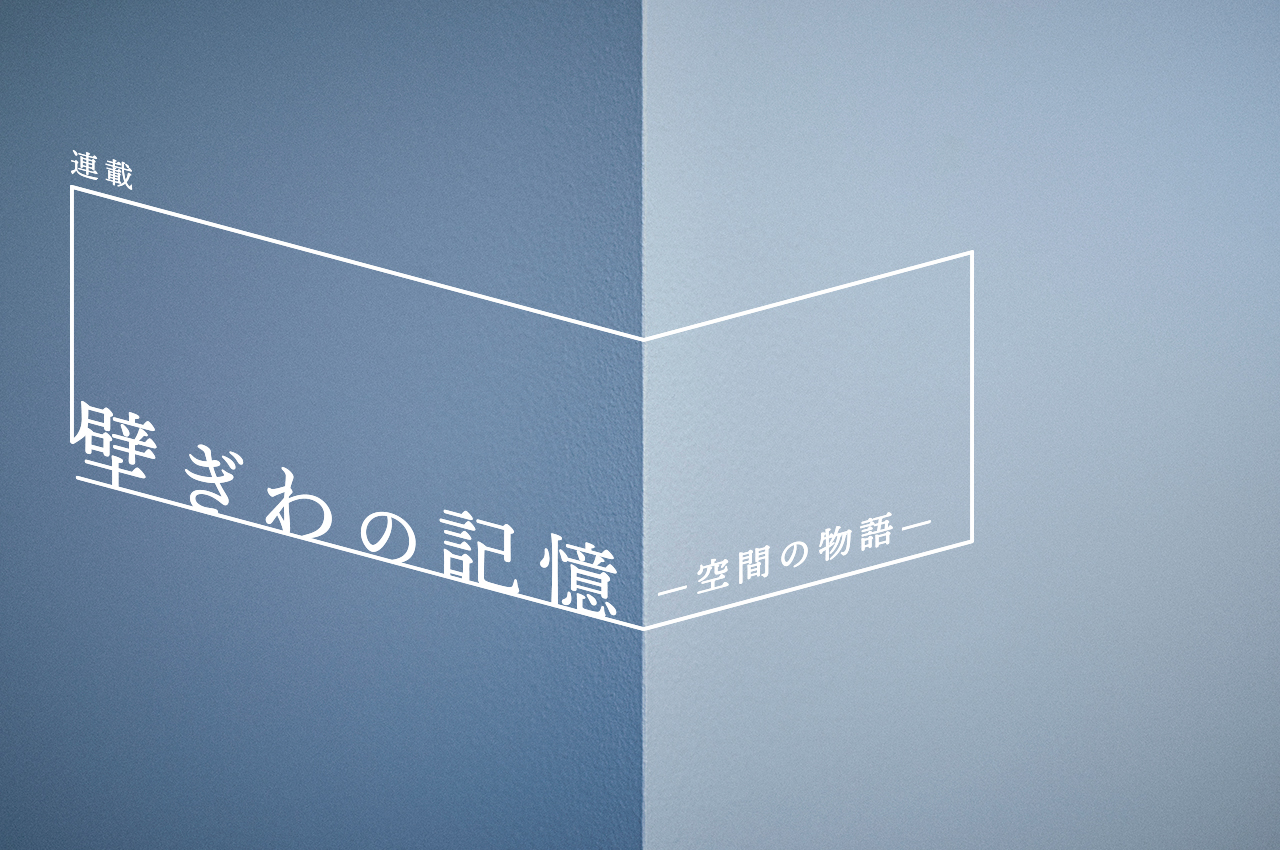2019年7月23日にAXISギャラリーで開催されたトークイベント「第2回 AXIS Design Round-table」。登壇者に本連載の書き手である大崎清夏さん(詩人)、第1回・第2回にそれぞれ登場いただいた工藤桃子さん、中山英之さん(建築家)のほか、環ROYさん(ラッパー)、ファシリテーターに鞍田 崇さん(哲学者)を迎え、連載のスピンオフとして企画しました。多領域にわたって活躍する今回のメンバーならではの視点から、約2時間の言葉と空間の関係性を巡るディスカッションの様子をレポートします。
言葉のイメージと現実を行き来する
大崎清夏さんは自身の活動を「世界の翻訳」と表現する詩人だ。詩作は内側に向いたものと思われがちだが、大崎さんはあるとき自分の「外側」にある物事を書こうと思い立ち、現在では人の暮らす場所や人と空間の結びつきなどをテーマに執筆している。この連載では大崎さん自身が建築を「体験」し、建築家から直接話を聞いて文章と詩を書いているが、連載で心がけていることを問われた際、聞いた話だけを書いているわけではないことを明かした。大崎さんは「建築家が全く言っていないことをひとつは必ず書くと決めている」と話す。これも翻訳のひとつと言えそうだ。
冒頭、言語に対するコンプレックスを告白した建築家の工藤桃子さん。抽象的思考を支えるための言語獲得の壁と言われる9歳までをスイスで過ごし、日本語とスイスドイツ語の両言語の狭間で育ったことがその要因だろうと話す。そんな工藤さんだが、設計の際には言葉と密接に向き合っている。「クライアントさんと話したり、現地を視察するなかでまずもやっとしたイメージを掴み、さらにヒントを引き出すように言葉をノートに羅列していく。その後具体化していくという流れで設計しています」(工藤)。対象が建築やインテリアなどスケールの大きなものになればなるほど、言葉の重要性は増すと話す。

中山英之さんは今までも度々スケール(縮尺)という考え方から建築が世界を変えうる可能性を説いてきた建築家だ。中山さんは学生時代、自身の美大の卒展で、建築科の展示が「実物がない」という理由で軽んじられる状況を目の当たりにした際、釈然としなかったと振り返る。実物がないのは事実だが、「建築家はスケールを軸にした考え方によって『ふたつの世界』を同時に生きることを可能にしている」と中山さんは言う。ふたつの世界とは、頭の中に生み出された世界と見えている実物の世界だ。中山さんは、建築家のみならず、私たちは皆ふたつの世界を生きているのだと話す。図面と縮尺の力によって頭の中に描き出された世界での「経験」と、見えている実物の世界とが重なったとき、その実物の世界が重層的に感じられてくると言うのだ。他の登壇者や会場の参加者のあいだにも新鮮な驚きが満ちた瞬間だった。

社会化された言葉
工藤さんは自分が話す言葉を「ファンタジーに飛ばせる言葉」と「確定的に使う言葉」の2種類に分けられると話す。自分のなかでイメージを飛躍させることのできる言葉と、設計の段階で使用する確定的な言葉だ。前者は同じ単語でも受け手によってもイメージするものが異なる場合があるが、後者は共通のイメージをつくり出す。
一方、中山さんは建築家の設計図書(図面や設計書・仕様書など)から読み取れる「関係性」に着目。学生のうちはひとりで模型も図面も手がけるが、社会に出たのち団体競技としての建築をつくる場合には、図面上の各部屋に室名をつけるなど、円滑なコミュニケーションを取るために社会化された言葉を使わざるを得ないと言う。

すると、ラッパーの環ROYさんは「図面は楽譜だし、室名は曲のタイトル。ひとつの建築を音楽アルバムと捉えられる。名付けざるを得ないというのも音楽が流通する上でジャンル分けしなければいけないことに共通している」と、自身も設計図書に似た作業を行なっていると語った。
未分化のもの、意味以前の言葉
環さんは新しい作品のリリースに向け、目下制作中だ。自身の言葉がどのように生まれるのかを問われると、制作に意識が向いている状態では「言語化」は難しいと話す。制作後であれば当時を振り返るかたちで語ることができるが、現在進行形で制作しているときには自身の内側で「未分化のものがずっと蠢いている感じ」だと言うのだ。

哲学者の鞍田 崇さんは環さんが制作中に体験しているような言語化以前の「生の体験」に注目。哲学者アンリ・ベルクソンの「時間と自由」に記された未分化な状態をどう言語化するかという問題に触れながら、「自分たちは実際のところ何を体験しているのだろう」と問いかけ、前述したイメージを共有するために社会化された言葉を一種の作法として受け止めつつも、そこには抜け落ちるものがあると指摘する。
では、未分化なものの言語化はどうすれば可能だろうか。その方法を巡って、大崎さんは自身が現在関わっている「音で観るダンスのワークインプログレス final」というプロジェクトでの、視覚障害者とともにコンテンポラリーダンスを楽しむための「音声ガイド」の制作過程について触れた。音声ガイドは視覚情報を音で置き換えることにより、鑑賞者にさまざまなイメージを浮かび上がらせるものだが、大崎さんはこのプロジェクトに多くの糸口を学んだと語る。
「正確に動きを描写するということはできるかもしれない。けれど、私たちがダンスを観るとき、単に動きを追っているわけじゃないですよね。じゃあ私たちがダンスを観るときに感じているものはなんだろうと考えると、情報保障としての音声ガイドでは届かない領域があるんです。そこを拾おうとすると、誰が書いても何かは抜け落ちてしまう。でも、詩という形式だからこそ掴めるものもあるんですね。そのなかで『ふとステップの秩序を蹴って』という1行を書いたとき、視覚障害の方が稽古でそれを聞いて『よくわかりません』と仰って。それは私が詩的な格好良さを追いかけて書いちゃった1行だったので、思いがけない鋭い批評にどきっとしました。何かを言語化しようとするとき、自分とは違う背景や前提のなかで生きている人の素直な感想ほど良い批評はないと思ったんです」(大崎)。

鞍田さんも「以前、音楽家の高木正勝さんとの会話で『言葉を意味で考えるからあかんのですよ』と言われたことがあった。言葉は、まず音。その音がどうやって出てきた音なのか。呻き声のように出てきた音が反復されてひとつの言葉になっていったんじゃないか。その言葉には単なる意味以前の、具体的なイメージがあるのかもしれない」と話す。「もっと言うと、その音のほうにすでに意味が埋め込まれているのかもしれない」と大崎さんが請け合い、未分化な「音」から言葉が生まれていることの意味に立ち返る場面も見られた。

初源的な体験と言葉
「言葉は脳で考えるというイメージがある人も多いと思いますが、実は身体なのかなと思う」と工藤さんが切り出したのは、環さんが即興でラップを披露した直後だった。次々と言葉をつなぎ、時にイメージを大きく飛躍させる環さんのラップは、あたかも特殊な訓練によって鍛えられた思考回路から紡ぎ出されたかのように感じられる。しかし、環さんは自身の即興について「言葉が持つ音のライン」と「言葉が持つ意味やイメージのライン」のふたつを行き来しながら遊ぶように行うと説明し、1回習得してしまえば階段の上り下りのように脳が覚え、忘れないと話す。

工藤さんは自身の生の体験と建築とのつながりを、(視覚障害者が観る映画などのセリフ以外を補う)音声解説者がどう表現したらいいのか分からない場面に直面した際、そのシーンを実際に体験することで新しい言葉を習得しているという話を例に挙げながら、「建築も空間に入ったときの自分の体感を体験として積み上げ、それを言語化しながら空間に図形化していく。図形化と言葉は似ている気がする。どちらも身体的で、プリミティブな体験が根底にある」と語る。
一方、中山さんは「プロダクトや建築の大部分がつくったつもりのないもので占められているのでは」と投げかけ、「全部の角を経験から導き出してバチバチに決めているのではなくて、ほとんどの部分がうっかりそうなってしまっているように思う。そのうっかりの割合が、自分のわかっていることよりも多いというのがいいところ」だと話す。

この発言は、建築がひじょうに大きく、人間の死後にも残り得るものだからこそ、「建築家は感情と淡々と距離を取りながら、ロジカルに感情の起伏を配置し遂行するべき」という中山さん自身のシステムを重んじる考えから発せられたものだろう。さらに、中山さんは一見真逆のように思われる「システム」と「自由」を同時に捉えてもいる。システムから生まれる自由について、マルタン・マルジェラが若い頃にデザインしたカーディガンのデザインを例に続ける。
「そのカーディガンは完全な十字形をしていて、真ん中に両方から開けられるファスナーがついている。彼がデザインしているのは、首と胴のサイズをただ同じくしているだけなんだけど、僕らはそれを見たときに、『ひとつ意味が打ち消された』と勝手に思うんですよね。襟、胴という名前はそのままに、余白が生まれる。それが襟でもあり胴でもあるということが知識として頭の片隅に残っているからこそ、僕らはそれが裏切られている状態に自由を感じる」、「僕にとって言葉とか名前をつけるっていうことと、そこにある解釈の可能性が自由っていうのは、ギリギリの背中合わせ。だから言葉は面白いと思う」(中山)。
会の終了時間が迫るなか、鞍田さんは人間がさらに良いシステムをつくり得る可能性に言及しつつ、「今の世の中は、だんだんシステムの効果を失っているように感じる。だからこそ、初源的な体験の場に立ち戻るようなゼロスタートを求められているのでは」と、情報だけではない世界との関わり方を改めて考える重要性に触れた。環さんもそれに呼応するように、「空間も言葉も、抽象度を少し上げると『人の知性』と言えると思う。知性っていう言葉の意味が一面的に捉えられがちだけど、生き死にに直結するような『身体的な知性』もある。知性を積み重ねていくことがいずれ『感覚』になるのかもしれない」と今の時代に求められる知性のあり方について語った。
ディスカッションを終えて
環さんが語る「未分化なものが蠢いている」状態は何かを生み出そうとする人の多くが共感するものだろう。自分の内側にあるイメージの言語化には困難がつきまとうもの。しかし、言語化を諦めずに繰り返し試みるとき、言葉は身体性を獲得していくのではないだろうか。その過程こそが、さまざまな表現分野の越境をも可能にするのかもしれない。空間やイメージの言語化と自分たちがつかっている言葉について、とことん向き合う2時間となった。
イベントの最後は大崎さんの未発表の詩、「渋谷、二〇一一」の朗読で締めくくられた。音となった言葉が残像となり、イベント終了後も会場に存在しているように感じられた。

渋谷、二〇一一
夜になり、東京メトロに乗って勤める会社から初台の築四〇年のマンションへ帰ってくるとき、ときどき呪文を唱えるように、私は思いだす。「あんたはまっすぐ自分ちに帰るでしょ、いつも帰るでしょ、あれじゃタクシードライバーの名がすたるじゃないの。」それは「夢みることをやめない」という詩のなかで詩人が言うせりふだ。
平日には毎晩、山手通りの歩道を歩いて帰る。引越してくる前からずっと工事中の大通りには、大勢のタクシーが走っている。内側からぼうっと光る赤いコーンが、混みあう灯籠流しのように、歩道と車道とタクシーの間を埋めつくしている。死んだ人みたいだ、と私は思う。歩道を歩く私も、流れつづけるタクシーも。山手通りは代々木八幡付近で小高く下道に覆いかぶさる。吹く風は少し冷たくなる。さっきまで一緒にいた会社の人たちやこれから顔を合わせるはずの同居人、明日会うはずのともだち、地上に残してきた人たちのことを、私は死んだ人の目で思いだす。
移動しつづける人はどこにもいない。どこにもいない人に憧れて、必死でどこにもいない人になろうとしていたはずなのに、いつも私はオーケーストアの角で道を左に折れた。灯籠流しの混雑を離脱して自分ちに帰り、あなたの薦める映画を観た。
必要とされるのは快いことだった。朝のお味噌汁をともに飲む相手として。オーケーストアの買い物をともにする相手として。会議に参加し資料をまとめ予定を調整する人材として。盛り上がりに欠けた会合のただの頭数として。私は喜んで出かけた。どこにもいない人になるために、どこにでもいるように心がけた。どこかにいて、誰かに見ていてもらうように心がけた。私の健康、私の活躍、私の発展を。何者でもないことを悲しがるのをやめるため、好きな服を着た。ときどき、ほんとにたまにだけど、死んだ人みたいだ、と思った。画面に没頭するあなたも、会議室の人びとも、会合に集まった頭も、好きな服を着た私も。山手通りの歩道を歩く私は、死んだみたいな私にとてもよく似合っていた。警察官の自転車が一台、私を後ろから追い越していった。生きてる人が見当たらなかった。生きてる奴どこだよと思った。ばかばかしい涙が溢れてきて、ばかばかしかった。
渋谷区の路上で、きちんとした身なりの会社帰りの歩行者や、小型犬を連れた夜の散歩の人に混じって、いずれ植込みの緑が車の吐き出す悪い空気を吸い取ってくれるはずのいくつもの四角い区画を横目に、泣きながら歩いている私は生きていた。ひとりぼっちで、満ちて、引いて、浮かんで、沈んで、晴れて、凪いで、澄んで、荒れて、濁って、湧いて、繋がって、切れて、揺れて、翻って、膨らんで、萎んで、潤って、乾いて、光って、溢れて、
生きて、どこにもいなかった。
※詩「夢みることをやめない」(伊藤比呂美・著/石内都・写真『手・足・肉・体―Hiromi 1955』筑摩書房刊 所収)からの引用箇所があります。