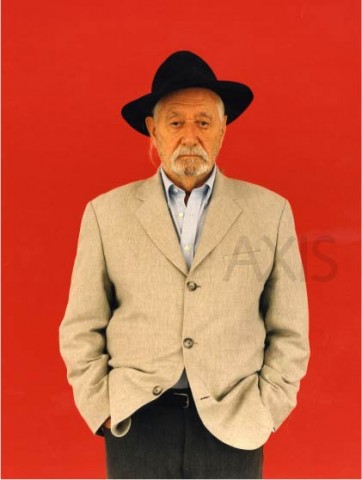この連載は、ミラノ在住のデザイナー橋本昌也による寄稿エッセイです。第2回は、日本でもよく知られるサローネ・デル・モービレ(ミラノ国際家具見本市)をイタリアからの視点で考察します。
サローネの歴史
1986年9月イタリアに渡った頃は、インターネットがなかった時代。オンタイムの情報もなく、ミラノでサローネが開催されていることは当然知る由もありませんでした。 ただただ雑誌のミラノ特集を読んで、憧れのデザイン都市に到着できたことで感動したのを覚えています。そのなか、特に印象に残るのが、道端にある新聞販売スタンドで建築デザイン専門誌「ドムス」が売られていたことでした。庶民が専門誌を購入する様子をみて、デザインがこれほど社会に浸透している事実に驚かされたのでした。
今回は、その世界でも有数のデザインイベントとなったサローネの歴史を遡って見たいと思います。

▲1986年のサローネのポスター
50年代の欧州における産業復興は一命題でした。まずは、ドイツの工業界が市場に向けて製品を紹介する見本市「ケルン・メッセ」を開催して、大きな成果を上げた。その後、北部イタリア都市の大手メーカーが同様のアプローチをはじめ、1961年9月に初の家具業界の見本市「サローネ・デル・モービレ」が開催された。当時の技術革新の旗手を担ったプラスチックを中心とした新素材がデザインされ、製品として市場に送り出された。特に、ミラノが伝統と革新の混在する世界でも唯一のクリエイションの土壌となり、デザインが潮流を作る原動力となることを実証しました。

▲1961年第1サローネの当時の様子。©Fondazione Fiera Milano
イタリアデザインとサローネ
1970年代に入りオイルショックで世界経済が冷え込むなか、そこで台頭したのが中部イタリアの中小企業でした。特に工芸技術を活用した商品が新たな推進力となり、ポストモダンという新潮流が担っていました。その中心が建築家のエトーレ・ソットサスが率いるメンフィスや倉俣史朗も参加したアルキミアです。
前グループのメンフィスは、ミラノ高級家具ブランドのカッシーナ社からカラフルな化粧板を配した家具、そして伝統木工やセラミックをカラフルで単純な幾何学形状で再構成した日常製品を市場に提案しました。この波は世界に伝播し、米国をはじめとする先進国で反響を招き、結果として、中小企業は生産体制の拡大を急遽取るようになるとともに、デザインが企業戦略の根幹であるという認識が確立しました。
また、この時期から見本市の会場外展示、いわゆるミラノ・フォーリ・サローネがはじまり、市内でのイベントが身近に提供されるようになった。90年代前後のサローネでの発表にはいつもワクワクしていたのを覚えていて、当時如何にデザインが活発に行われていたかが伺えます。

▲Bookshelf Carlton, Ettore Sottsass, 1981
合板をカラフルな化粧板で装飾した独創的な書架。

▲Switch rompitratta, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1968
60年代後半のデザインであるが、いまだに古びず使われている名品。
サローネの近年の傾向
その後、2010年初頭から現在までのサローネは一変しました。老舗イタリアブランドはことごとく経営権を国内外の会社運営専門家に任せたため、デザインの指針は独自性からリスク回避を重要視する方向へとシフトし、イタリアらしいインパクトのある創造的な作品が少なくなってきたと実感します。同時に家具に留まらない広い領域の製品と、国内外の若い世代のクリエーターがデザインを発表する場へとサローネが転身しました。
2年ぶりに全面再開した今年のサローネは、デザインコミュニティーの結束を出展者と来場者が共有する場となりました。さらに、鉄や石といった道具文化の素材回帰や、柔らかい感触の素材感といった傾向は、時代背景を表す新傾向と見ることができます。
グローバル化がより加速する今、デジタル技術がデザインにより深く関与する時代となっています。アナログとデジタル世代が混在し、ソーシャル文化融合がより活発化するなか、デザインが自立して文化のイニシアティブを担うべき時がきていると期待してはならないです。
こうしてサローネを振り返ると、モノづくりとは、ふと身の回りにある物に興味を持ち、その時点で使いやすく創造しまわりに問うことなのだと、改めてデザインの原点をつくづくと思い出させます。

▲2022年サローネ。年間のコロナ自粛から開放され、多くの来場者が戻ってきました。
© Diego Raver/Courtesy Salone Mobile.Milano